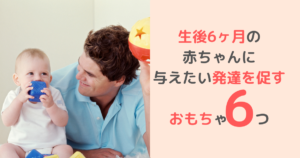2歳や3歳以降、子どもが少しずつ自分でできることが増えると、「周りのお友達も何か始めているし、何か習い事や知育を始めた方がいいのかしら」と悩む方が増えてきます。
もちろん新しくお習い事を始めてもいいのですが、子どもの教育や知育にはボードゲームやアナログゲームがおすすめです。
ここでは「ボードゲーム」や「アナログゲーム」と聞いてもピンとこない人に向けて、以下3つをお伝えします。
- ボードゲームやアナログゲームとは何か
- なぜアナログゲームがおすすめなのか
- 王道アナログゲーム3選
- デメリットやよくある質問
1つずつ説明しますね。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①ボードゲームやアナログゲームとは何か
ボードゲームとはいわゆるすごろくと言った、盤面を使ったゲームです。
人生ゲームなどは聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
またアナログゲームとは、トランプ、花札、カルタなどテレビゲーム以外のことをさします。
アナログゲームという意味ではボードゲームも含まれます。
これらアナログゲームの歴史は大変古く、日本だけではなく海外でも大変人気があります。
また、ヨーロッパではアナログゲームの人気が高く、大人も子どもも楽しめる面白いゲームがたくさん開発されさまざまな賞を受賞しています。
②なぜアナログゲームがおすすめなのか
アナログゲームは、
- 考える力が鍛えられる
- 手先や指、目を鍛えられる
- 駆け引きなどの先を読む力が鍛えられる
- 足し算、引き算、掛け算などの計算力が育つ
- 長く遊べる
このように、子どもの知育にとても向いています。
1つずつ説明しますね。
①考える力が鍛えられる
アナログゲームは遊びながら考える力を鍛えることができます。
例えば、
- 今の状況を把握する
- 頭の中で整理する
- 戦略を考える
このような一連の考える力は、プリント学習の学びだけでは再現できません。
幼いころからたくさん経験しておきたい時間です。
②駆け引きなどの先を読む力が鍛えられる
トランプでのババ抜きをしているとき、最後に二人残ってどちらが先に勝つことができるのかとても緊張します。
駆け引きや先を読む力も考える力の一つですが、これらの力も生きていく知恵として必要です。
③勝ち負けが常日頃から体験できる
子どもは勝ったり負けたりする経験をする必要があります。
負けることで、次はどのようすれば勝てるのか考え、改善するようになります。
また勝ってもどうすれば勝ち続けるのか考えるでしょう。
そして何よりも一番経験して欲しい、負けたときに自分の感情とどう向き合うのかを考えるチャンスです。
今まで子どもに関するスクールを運営して感じることは、成長していく子は、いかに自分の機嫌を自分で取るのかをわかっている子です。
ときには悔しくてたくさん泣くことも子どもには必要です。
しかし、どこかのタイミングでその状況から脱して、次のステージに向かうには自分で気持ちを切り替える必要があります。
自分の気持ちを上手に切り替えるためには、小さいころから勝ったり負けたりする経験がとても重要です。
また上手に気持ちを切り替えるには、一人で深呼吸をして自分を整えることも必要なスキルの一つです。
④手先や指、目を鍛えられる
トランプを混ぜる、オセロをつまんでひっくり返すなどの行動は、子どもの手先や指先を鍛えます。
また何よりも幼少期に鍛えておきたい、目と手の協応(目で見たものを手でつかむなどの操作)をたくさん経験できます。
目と手の協応は大人にとって当たり前にできる動作ですが、まだ目の機能が発達していない子どもたちにとってはたくさん経験すべき動きです。
テレビゲームを否定するわけではありませんが、テレビゲームだとどうしても長時間視点を固定し目を動かしませんし、目を動かす幅や手指の動きも限られてしまいます。
しかしアナログゲームであれば五感や全身を使うので、テレビゲームでは味わえない経験ができるでしょう。


⑤足し算、引き算、掛け算などの計算力が育つ
人生ゲームでサイコロを振り、コマを進める。
大人からするといたって普通のことですが、これには足し算、引き算などの数の学びがたくさん含まれています。
遊びながら自然と足し算などを学べるアナログゲームは子どもたちにとって最高の教材です。
よく「プリント学習による反復練習でも計算は早くなりますが、何がちがいますか」と質問をいただきます。
普段から数遊びをして、足し算の意味や数量感(100個ってこれぐらい、半分てこれぐらい)といった実体験をたくさんしてきた子どもたちにはプリント学習はおすすめです。
しかし、そのような実体験がないままプリント学習のみ進めると、文字のパターンだけ覚えてしまい、計算はできても文章問題はできないなどの問題も起こります。
詳しくはこちらの記事を参照してください。
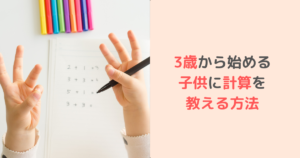

⑥長く遊べる
ボードゲームやアナログゲームの多くが長く遊べます。
トランプなども枚数を調整すれば2歳児でも神経衰弱ができますし、大きくなったらトランプ全てを使ってレベル調整をすれば楽しく遊べるのでコストパフォーマンスも良いです。
③王道アナログゲーム3選
色々なアナログゲームが販売されていますが、長く遊べて、遊び方のバリエーション、飽きのこないおもしろさで考えると、
- トランプ
- オセロ
- 人生ゲーム
の3つがおすすめです。
上記ゲームであれば3歳ぐらいから始めることができます。
トランプであれば、ババ抜きやじじ抜き、枚数を減らした神経衰弱、スピード、大貧民など楽しく遊ぶことができます。
また普段から数に触れることができるので、その先の算数にも繋がります。
オセロも子どもが喜ぶ遊びの一つです。
一つでオセロだけでなく、将棋やその他のゲームもできるものもあるので、探してみましょう。
人生ゲームも順番を守ったり、ルーレットを回したりと社会性が育まれます。
これらを揃えて物足りなくなったら、花札や海外製のボードゲームなどを購入するといいでしょう。
一個人のおすすめにはなりますが、HABAというドイツ製のゲームメーカーは低年齢からできるおもちゃをたくさん開発しているので大変おすすめです。
④デメリットやよくある質問
アナログゲームのデメリットはどうしても対戦相手が親になることが多いので、親が時間的に拘束されることです。
「1回だけよ」と言っても、ゲームが終わるともう一回やりたいと子どもがお願いしてきます。
そのため、ゲーム購入時点では楽しく遊べるのですが、回数を重ねていくとどうしても親が飽きてしまいます。
ただし、塾や習い事では得られない力を身につけることができるので、付き合ってあげましょう。
また、「どれぐらいの頻度で遊べば良いですか」と聞かれます。
この質問には、どれぐらい遊べば知育的な効果があるのか、時間的に大変なので最低でもどれぐらいの頻度で遊べばいいですかという意味があると思っています。
知育的な効果に関しては子どもの年齢と発達によって吸収することが違うので年単位とお答えしています。
そのため、焦らずに取り組むことが必要となります。
平日の暇なときや週末など時間のあるときに細く長く続けましょう。
また、近年テレビゲームは持っているけれども、アナログゲームは持っていないご家庭も増えてきたので、お友達が遊びにきたときなどにルールを教え、子ども同士で遊ばせましょう。
ゲームを提示するさい、「ゲームは勝ったり負けたりします。勝っても負けても泣かずに楽しくあそべますか」と聞くと、子どももルールを理解しスムーズに進むでしょう。
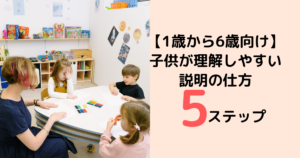

まとめ
ボードゲームやアナログゲームは、プリント学習だけでは習得できないさまざまな学びを身につけることができます。
アナログゲームは費用対効果が高い知育です。
まずは王道のトランプ、オセロ、人生ゲームを購入し、子どもにゲームの面白さを教えてあげましょう。