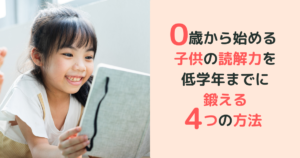長年子どもの教育に関わるスクールを運営していると、多くの親から「我が子は全く集中力がありません。どうすればいいのでしょうか」とたくさんの相談をいただきます。
基本的に子どもの集中力は年齢プラス1分と言われています。
3歳であればプラス1分で4分程度です。
しかし、子どものことを知り、環境を整えることで子どもの集中力は大幅に伸ばすことができます。
事実、私が運営するスクールに通う多くの子どもたちは1時間以上集中力を発揮します。
それではご家庭で子どもの集中力を伸ばすには、どの様な取り組みをすればいいのでしょうか。
結論から伝えると、集中力に関しては子どもを3つグループに分けて、それぞれの特徴ごとに対応をすることが最初に必要だと感じています。
- 運動には集中するが、勉強など学ぶことに集中できない子
- 落ち着いて学ぶことには取り組むが、運動には集中できない子
- そもそも集中力のない子
それぞれ1つずつ対応策をお伝えしますね。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①運動には集中するが、勉強など学ぶことに集中できない子
このタイプの子は運動が大好きで、自分の好きなことには集中しますが、静かに座って何かに取り組むことが苦手です。
この様な子を分析すると、多くの場合運動のし過ぎが挙げられます。
確かに体を動かすこと、適度な運動は子どもたちの心と体を鍛え、結果脳にも良い影響を与えます。
しかし、運動のし過ぎになると、
- 常にソワソワしている
- 椅子に座れない
多くの場合この様な共通点が見受けられます。
そして、その様な子どもは本を読んだりパズルをしたり、知的な活動に興味を示しません。
勉強も勢いで取り組み見直しなどもしません。
このタイプは、運動の量を見直すことで子どもが落ち着きます。
よく、「子どもがスポーツをやりたがっているから好きなものをやらせてあげたい」と言ってくる親もいますが、サッカーやバスケットボールなど常に有酸素運動が必要なスポーツを組み合わせています。
一部体力のある子どもは両方掛け持ちしても平気な子どももいますが、多くの子どもの場合、運動量が過剰過ぎて体力的にきつく感じている子どもも多いのです。
体力的にきつく感じていると言いましたが、子どもたちに聞くと「別に疲れてないよ。もっとやりたい」と言うのですが、明らかに動きが散漫で、細かい動作をすることができていません。
子どもの意志を尊重することも大事ですが、その様な気配を感じたら親子で話し合いをし、親がバランスを整えてあげましょう。
②落ち着いて学ぶことには取り組むが、運動には集中できない子
1番の運動が大好きな子の逆で、運動し過ぎない子どもも問題が発生します。
この様な子どもたちは体力がないので、長時間何かに取り組むとすぐに疲れてしまいます。
年齢によっては運動の好き嫌いもあるでしょうから、普段から散歩をする、または運動に挑戦するのであれば、ヨガなど「型」を学ぶスポーツがおすすめです。
走り回ることだけが体力向上に繋がるわけではありません。
子どもにあうスポーツを見つけて全身の血流を促進させましょう。
③そもそも集中力のない子
運動も学びも何にしても無気力な子どもや集中力がない子どもを観察すると、
- 習い事のし過ぎ
- 砂糖の摂り過ぎなど食事の問題
- 睡眠の問題
これら3つが挙げられます。
①習い事のし過ぎ
現代っ子はとても忙しい子どもが多いです。
毎日一つだけではなく、二つ三つと習い事を掛け持ちしてオーバーワークな子どもがいます。
運動と同じように、「子どもがやりたいものをとにかくやらせている」と親は言いますが、子どもの集中力は既に限界を迎えています。
子どもたちの習い事の様子を見学すると、親が一緒のお迎えのときはとても元気ですが、一度親と別れると元気ではなくなり動きが散漫になります。
「習い事が多くて大変ならば、一度おやすみしたら」と提案をしても、子どもたちは「休みたくない」と言って惰性で続ける子どもも多いものです。
子どもには家でぼーっとする時間、何もしない時間も必要です。
過剰になり過ぎない様親がコントロールをしましょう。
②砂糖の摂り過ぎなど食事の問題
砂糖の摂り過ぎは、一時的には元気になりますが、子どもたちの体を疲れさせます。
小学校に入学し友達との付き合いなども増えて、砂糖を食べない生活は私は無理だと思います。
しかし、親がある程度コントロールしなければ、常に砂糖がふんだんに含まれている飲み物やお菓子などを食べ、結果食事を取らない子も多くいます。
適度な砂糖は脳を活性化しますが、摂り過ぎはよくないので、1日3食の食事をバランス良く食べ、そして嗜好品としてお菓子やジュースを飲みましょう。

③睡眠の問題
「夜遅くまでスマートフォンで動画をみていた」
「ゲームをしていた」
など現代の世の中には子どもの睡眠を妨げるアイテムがたくさんあります。
子どもも友達との人間関係などがあり、そう言ったものをやらないという選択肢はなかなか難しいかと思いますが、せめて夜20時以降は親がゲーム機やスマートフォンを預かるなどして画面を見る時間を調整しましょう。
ゲームやスマートフォンだけが子どもの睡眠悪化の原因ではありません。
しかし、私たち親ですら寝る前にメールやDMがあったら、寝ようと思っても返事をしてしまいます。
ましてや脳が未発達な思春期の子どもたちは、そういった誘惑をコントロールすることは親の私たちよりとても難しいのです。
使ってはいけないのではなく、調整するというスタンスで、電子機器と上手に付き合いましょう。

④子どもの集中力を鍛える遊び
まずは環境を調整し、子どもがこれらのうちどれに当てはまるかを分析したあと、集中力を鍛える遊びに取り組みましょう。
対象年齢は3歳から12歳の間で楽しみながら集中力を鍛える遊びを選びました。
- 折り紙
- パズル
- ボードゲーム
- トランプ、花札、将棋などのアナログゲーム
- 読書
どれもみなさんが知っているものばかりかと思います。
しかし、電子機器によるゲームでは体験できない、手先のコントロールや、五感を使う、相手の顔色を伺う、戦略を練るなどたくさんのことが一度に経験できます。
子どもにあったものを選んで、ぜひ取り組んでみましょう。


まとめ
既に体力、精神が尽き果てている子は集中力を発揮することはできません。
まずは、生活を整える事から始めましょう。
子どもの体力は無限ではありません。
子どもの取り巻く環境、そして、睡眠や食事が整わなければ、基礎が乱れてしまうのですべてが空回りになります。
家庭の中で基礎を固めてから、バリエーションを増やしていくことで親子のストレスも軽減されスムーズに知育に取り組むことが出来ます。
まずは子どもを観察してみましょう。