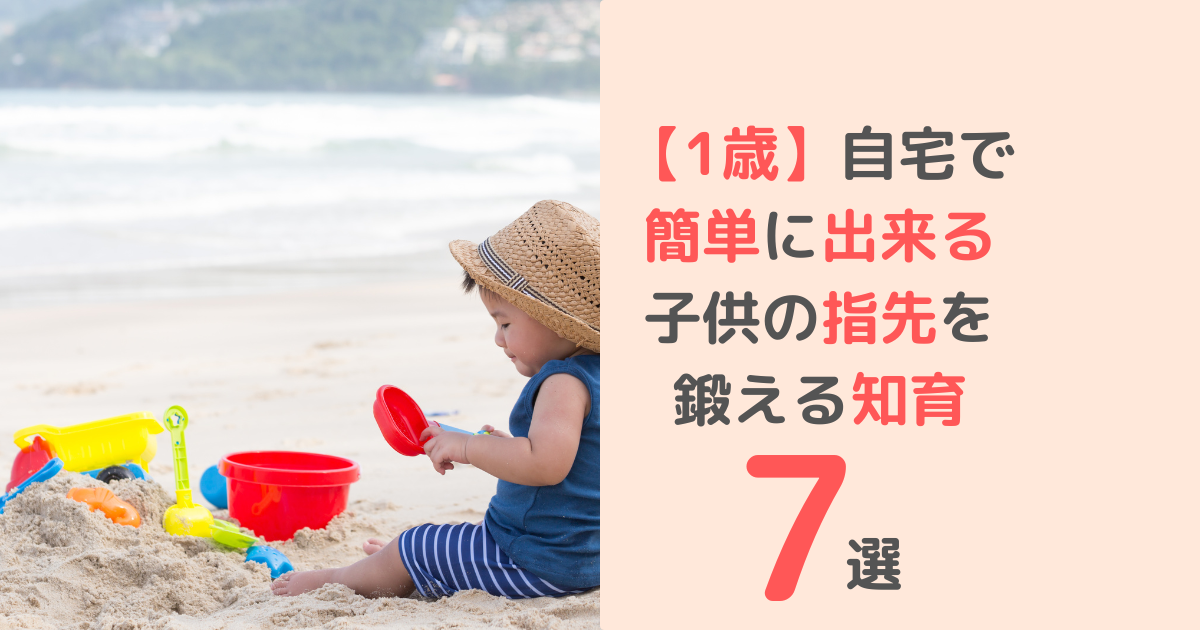子どもは1歳になると、手を全体で使ったにぎる動作から、指2本でつまむことができるようになります。
この時期は手先を器用にするために、家でどのような遊びをすればいいのでしょうか。
おすすめは、
- シール貼り遊び
- 1〜9ピースのパズル
- 楽器遊び
- 新聞遊び
- ひも通し
- 手遊び歌
- 絵の具遊び
これらの7つがおすすめです。
1つずつ説明しますね。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①シール貼り遊び
この時期からシールブックで遊ぶことも、手先を使う良い遊びの一つです。
1歳を過ぎると、しゃべることができなくても、絵と言葉を頭のなかで結びつけ始めます。
例えば、犬の絵をみたら「いぬ」とは言えなくても、犬がどれかがわかってきます。
そのため、ただシールを貼るだけではなく、一緒に語彙を増やす遊びをしてみましょう。
例えば、犬と鳥の写真を出して「犬にシールを貼ってください」と声をかけ、子どもにシールを貼ってもらいましょう。
もし難しいようでしたら、犬と鳥など二択にして、どちらかに貼る練習を進めていきましょう。
シールは、画像にあるメーカーが安くて大量にシールが入っていておすすめです。
この時期は、シールのサイズは、直径1.5cmがおすすめです。
また以下画像のように、子どもがシールをつまみやすいように、親が事前に折ってあげましょう。
②1~9ピースのパズル
この時期はピース数が少ないパズルもおすすめです。
パズルは考える力、集中力、観察力、想像力なども身につきますが、同時につまみが付いているパズルを使ってつまむ動作を学んだり、パズルをはめることで微細な手の動きを学ぶこともできます。
お子さんが楽しく挑戦できるピース数を選んで下さい。
親子で会話を楽しみながら「この形はまるだね」「”この動物はクマだね」と、このようにコミュニケーションを取れる所も魅力の一つです。
ただし、慣れて来てどこにどのピースが入るかを理解してしまうと飽きてしまうのでそのときは、レベルアップしたパズルの買い替えをおすすめします。
③楽器遊び
0歳後半から1歳の時期にかけては、楽器遊びもおすすめです。
最初は木琴やタンバリンなど打楽器がおすすめです。
自分で叩いたら音がでるという反応は、子どもにとっても良い刺激になります。
また、1歳中頃からはカスタネットも良いでしょう。
木琴やタンバリンより楽器のサイズが小さくなるので、狙った場所に手を打つことは手だけでなく、目も同時に鍛えることができます。
1歳後半は鈴遊びがピッタリです。
鈴遊びは、
- 腕全体を使って鈴をふる
- 手首をスナップして鈴をふる
- 細かく鈴をふる
とさまざまなバリエーションがあり、長く使える楽器の一つです。
④新聞遊び
新聞は、
- ビリビリ破る
- 新聞をちぎる、丸める
- 丸めた新聞を投げる
など、さまざまな応用遊びができ、おすすめです。
①ビリビリ破る
赤ちゃんの時期に、紙を破るイタズラをして困るという相談もありますが、赤ちゃんからすると理由があります。
子どもにとって、ビリビリと新聞を破る音、感覚はとても魅力的な反応です。
②新聞をちぎる、丸める
新聞を「破る」と「ちぎる」では、実は手の動かし方が違います。
新聞を破るときは、手を全体使って前後にひねるので、スプーンをもつ動きにつながります。
新聞をちぎる動作は指先を使うので、つまむ動作に近い動きです。
また、新聞を丸める動きは手首全体を使います。
③丸めた新聞を投げる
せっかく新聞を使った遊びをするのであれば、最後は新聞を丸めてボール遊びをしましょう。
新聞ボールであれば怪我もしません。
体全体を使って投げても良いですし、ボーリング玉のように転がすことも良いでしょう。
家に新聞がない場合は、読まなくなった週刊誌や雑誌などが紙の厚みも丁度よく、使い勝手が良いです。
⑤ひも通し
ひも通しは、幼少期に必ずやっておきたい遊びの一つです。
最初はビーズから始めましょう。
ビーズはサイズで難易度が変わってきます。
穴の入り口から出口までの距離が短いものから挑戦させましょう。
この時期は、ビーズの数は5個から10個を目安に挑戦しましょう。
上手にできるようになったら、ビーズのサイズを大きくしましょう。
ビーズのサイズが大きくなると、ひもをより奥に入れないと出てこないので、より難しくなります。
なお、ひもはアグレットで先が固くなっている物が扱いやすくなります。
ひもの反対側は、ビーズが抜けないようにコブ結びにしておきましょう。
⑥手遊び歌
1歳ごろになると、手遊びも少しずつ出来るようになります。
- トントントントンひげじいさん
- グーチョキパーでなにつくろう
- あたまかたひざポン
- 1本橋こちょこちょ
など定番の手遊びを親子でたくさんしましょう。
⑦絵の具遊び
絵の具遊びは感覚と色彩も一緒に鍛えることができる遊びです。
絵の具用の筆を使うのではなく、手で直接さわらせてあげましょう。
クリアファイルの上に絵の具を少量ずつ出して、手で混ぜてみましょう。
子どもが自由に歩き回ると片付けが大変になるので、子ども用の椅子に固定して、テーブルの上で遊ばせると、片付けも最小限ですみます。
まとめ
1歳になると、身体のコントロールが自分の意思によって効くようになります。
お子さんも出来るとうれしくなりますし、うれしい気持ちを表現します。
見ているママパパも成長を感じられる年齢だと思います。
個人差はありますが、出来る事をどんどん増やして自信を付けさせてあげましょう。