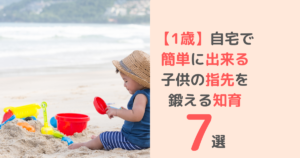子どもは2歳になると、それまで手を使ってきた経験と発達段階が重なり、複雑な動きができるようになります。
そんな2歳児におすすめな手先を鍛える遊びは次の6つになります。
- シール貼り
- 手をひねる、ねじる遊び
- トング・ピンセットを使ったつまむ遊び
- ねんど遊び
- 折り紙遊び
- ハサミの練習
1つずつ説明しますね。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①シール貼り
シールが貼ってある紙から、子どもが自分の力でシールをはがして貼れるようにしましょう。
シールをはがすことは、大人からすると簡単な作業に見えますが、両方の手を使い紙を曲げて、シールをはがす作業は子どもにとってとても難しい動きです。
シールは、画像にあるメーカーが安くて大量にシールが入っていておすすめです。
この時期は、シールのサイズは、直径1.5cmがおすすめです。
今まで自分でシールをはがす経験をあまりしてこなかったり、手先を上手に動かせないようであれば、画像のようにシールを最初から折り目をつけてあげると、子どもはシールをはがしやすいです。
慣れるまではサポートしてあげましょう。
②手をひねる・ねじる遊び
この時期になると、手を使った、貼る・叩く・引っ張るなどの動作に加え、「ねじる」運動が出来るようになる子どもも増えるでしょう。
おすすめは子ども用のネジのおもちゃです。
左手では抑えて右手で回すようにひねる・ねじる練習をたくさんしましょう。
ネジのおもちゃを用意できない場合は、ペットボトルを使って、子どもが一人でペットボトルのふたを自分で開けられるように練習をさせてあげてください。
ペットボトルを使うときは、ふたを少しゆるくしめてから子どもに渡してあげましょう。
「しめる」動作は1ステップ高い難しい作業です。
まずは、ひねって、ねじって外す知育から始めてください。
近年では手をかざせば水道から水が出たり、トイレも自動で水が流れるため、普段の生活の中において幼少期から手をひねる・ねじる経験が少なくなりました。
そのため、大人が用意してあげないと、経験しないまま成長のチャンスを逃してしまいます。
たくさん経験させてあげましょう。
③トングやピンセットを使ったつまむ遊び
2歳児であれば日常で使う道具を使えるようになります。
自分の手指と道具を通して、作業していきます。
道具を使わせる場合は、必ず最初にお父さん、お母さんが使い方の見本を見せましょう。
道具を正しく使えるようになると、今後一人で使うときに怪我をする危険性が大きく減ります。
この時期はトングやピンセットをつかったつまむ遊びがおすすめです。
遊び方は、お皿2枚を用意し、片方に1㎝程の滑りにくい素材のつまみやすい物を10個用意してください。
私たちが運営する教室では、ミニ消しゴムを使っています。
「つまんでパー。つまんでパー」と分かりやすいかけ声と、動作の見本を見せてから練習していきます。
右から左へつまんでものを移動します。
全部移動できたら、左から右へ移す練習を行います。
把握の弱いお子さんや上手に一人でできない場合は、親が手を添えて手伝ってください。
④ねんど遊び
ねんど遊びは、ねんど独特の感触で、日常生活の中だけでは経験できない感覚を味わえます。
ねんどをこねて丸める動作や、ヘビを作るように寝かして伸ばす動き、ちぎって小さくする作業など、指先を使う動作がたくさん含まれています。
また、型を使ってくり抜いたり、ねんどベラを使い、お料理のごっこ遊びもでき、楽しい時間になります。
お子さんが自由に形を作れるのは、発想力や想像力に繋がります。
子どもが一人で自由にねんどを使って遊ぶのもいいですが、親が作った形を真似をして作らせる遊びも、観察力やコミュニケーション能力が向上するのでおすすめです。
⑤おり紙遊び
大人からすると、正方形の折り紙を半分に折ったら三角になることは当たり前ですが、子どもからすると不思議な感覚です。
おり紙を折ったり、折ったおり紙を開いたりすることで、手先の遊びだけではなく、図形感覚や展開図などが理解できるようになります。
おり紙の角と角をあわせたり、端と端をしっかりそろえることは、手の細かい動きが必要で大変難しい作業です。
また、おり紙を折れば折るほど小さくなったり、正方形から形が変わっていく経験は子どもの想像力と五感を大きく刺激します。
たくさんおり紙遊びをしましょう。
⑥ハサミの練習
ハサミは必ず最初に使い方の説明をします。
- ハサミは誤った使い方をすると怪我をすること
- 持ち方
- 人に渡すときの渡し方
このようなことを丁寧に説明しましょう。
用意する紙は、ハサミの口を開いて1回で切れる紙がまずは基本です。
素材も薄い画用紙がおすすめです。
ハサミを使って自由に切る練習もいいですが、親が線を書いて、線にそって切る練習もおすすめです。
ここでも「ギューしてパー。ギューしてパー」子どもが分かりやすいフレーズを言いながら進めると、耳からも動作が記憶され定着しやすいです。
1回切りが上手になって来たら2回分ハサミを進めないと切れないサイズへとステップアップしてください。
まとめ
2歳児では、基礎を発展させてできることを増やしましょう。
幼いお子さんは利き手はまだ決まっていないので、両手をバランスよく使えるよう促してみましょう。
2歳になると自我が芽生え俗にいうイヤイヤ期を迎えるお子さんもいます。
そんな中でも指先を使った遊びは、お子さんが興味を持って取り組みやすい活動です。
お父さん、お母さんのマネをしていろんな道具を使ってみたい時期になりますが、子ども用サイズのものを与えましょう。