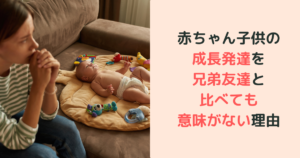赤ちゃんは6ヶ月ごろになると平均的にどんなことができるようになるのでしょうか。
ここでは6ヶ月ごろを迎えた親子に向けて赤ちゃんの発達の目安をお伝えします。
平均的な赤ちゃんの発達段階を知ることで親子共に毎日が楽しくなります。
なお、発達には個性や個人差があり一人一人異なります。
そのため、発達の度合いはあれどいずれできるようになるので過度な心配はせずおおらかな気持ちで見守りましょう。
親ができることは焦ったり子どもに強制をすることではなく、発達を促す手伝いと環境を整え信じて待つことです。
もし子どもの発達について心配であれば自身で判断せず、必ず病院に行って相談してください。
それでは一つずつみていきましょう。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録をよろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、特典で0カ月から12カ月の赤ちゃんの発達の目安一覧表PDFデータ、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
6ヶ月の時点でできるようになる全身運動
健全な発達には全身を動かし体幹を鍛え使えるようになることが重要です。
6ヶ月の時点で赤ちゃんは、
- 仰向けの状態で手で足をつかめるようになる
- 仰向けの状態で手で足をつかみ、口に入れることがある
- 仰向けの状態で両足をバタバタとキックすることができる
- うつ伏せの状態で胸と頭を持ち上げることができる
- うつ伏せの状態で腕を伸ばし欲しいおもちゃをつかめるようになる
- うつ伏せの状態で体を回転したり前後に動かすようになる
- 寝返りが上手にできるようになる
- 一人で座れるようになる
- 足の筋肉が徐々に発達し、脇の下を持って抱っこをすると足をバタバタさせることができる
このような全身運動の様子がみられます。
一見どれも普通の動作ですが、赤ちゃんはこのような動作を毎日繰り返すことで体幹を鍛え、その後のハイハイや歩く動作のために準備をしているのです。
また発達の順番として、
- 体幹
- 肩や腕
- 手先
と発達していきます。
将来手先が器用になるためには乳幼児期からの全身運動は大きな影響を与えます。
たくさん全身を鍛える遊びをしましょう。

6ヶ月の時点でできるようになる細かい体の動き
次に細かい体の動きをみていきましょう。
- おもちゃを右手、左手と受け渡すことができる
- おもちゃをつかみ、手放すことができる
- ものを持ち上げることができるようになる
- 手を使って細かいものをかき集めることができるようになる
- 持っているものを振り回し叩きつけることができる
- 持っているものを口に入れる
このようなことができるようになります。
この時期一番多い親からの相談は、
- 持っているものを叩きつけたり投げたりすること
- 持っているものをなんでも口にいれてしまうこと
です。
1つずつ説明しますね。
①持っているものを叩きつけたり投げたりすること
持っているものを叩きつけたり投げたりする姿を見ると、「このまま乱暴な子どもになったらどうしよう」「投げたおもちゃで他のお友達が怪我をしないようにやめさせよう」と思う親が多いようです。
また、この時期赤ちゃんが笑顔で親の顔を叩きやめさせたいと思っている親も多いです。
これらはバンギングと言い多くの赤ちゃんが6ヶ月から1歳前後まで行い続ける赤ちゃんの動作です。
赤ちゃんはバンギングをしながら、
- 肩周りの筋肉を鍛える
- 力加減を学ぶ
- 持っているものの素材を確認している
- 振り回した結果どうなるのか観察している
このようなことを学んでいます。
そのためバンギングを静止せず「今はバンギングをしてさまざまなことを学んでいるんだな」という気持ちで見守りましょう。
もし投げられて困るものが赤ちゃんの身の回りにあるのであれば撤去します。
6ヶ月ですとまだ早いですが1歳前後になったら太鼓や木琴などを与えることで赤ちゃんの興味を刺激するのでおすすめです。
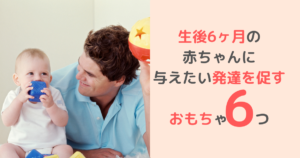

赤ちゃんは興味が満たされ力加減を学び終えるとこのようなバンギングは通常消えていきます。
1歳6ヶ月以降、
- 自分が不機嫌で八つ当たりのためものを投げる
- ものを投げてお友達に危害を与える
このような行動がみられるようであれば、子どもの目をみながらいけないことはいけないと感情を込めず淡々と伝えましょう。


②持っているものをなんでも口にいれてしまうこと
「赤ちゃんが持っているものをなんでも口に入れてしまう」このような悩みもよくいただきます。
これも赤ちゃんにとっては学びと成長のプロセスの一環です。
なんでも吸収する0歳から3歳の間、子どもは生まれてきた環境に適応するために五感を通じて大量の情報を学びます。
特に触覚を通じた刺激は赤ちゃんの脳を刺激します。
そのため誤飲の心配がなければ赤ちゃんが納得するまでさせてあげましょう。
よく絵本を口に入れ絵本をダメにしてしまうという相談を受けますが、絵本が赤ちゃんの唾液でダメになってしまうのであればボードブックや布絵本などを与えましょう。
絵本に限らず素材を変えるなどして環境を整え、赤ちゃんの興味を満足させてあげることが健全な発達を促し賢い子どもになる秘訣です。

6ヶ月の時点でのコミュニケーション能力
6ヶ月になると赤ちゃんはさまざまな方法で会話を始めます。
大きな声で笑顔で奇声を発したり「ばばばば」など声を発します。
また、今までは一方的に話しかけていたのが親子で交互で会話できるようになります。
ママ・パパが話し終えると、次は赤ちゃんが話すようになります。
また大きな音に反応するようになったり、親が黙っていると喃語を使って語りかけるようにもなります。
育児のススメ-300x158.png)
6ヶ月の時点での認知スキル、社会性、感情について
6ヶ月になると赤ちゃんは他人を意識し始めます。
特に一番身近である親には最大限の興味を示し親が遊んでくれることに対して最大限の幸せを感じます。
また親以外の他人にも興味を持ち始め人見知りが始まるのもこの時期です。
親以外の他人に興味が沸き近づいては泣いたりを繰り返すこともあります。
まとめ
6ヶ月時点での赤ちゃんの平均的な成長についてお伝えしました。
この記事を読んでいる方は、
- 子どもの発達に不安がある
- 子どもがどのように成長していくのかがわからない
- 将来自立した子や賢い子になって欲しい
などさまざまな目的を持っていらっしゃると思います。
子どもの発達には個性があり一人一人違います。
親ができることは他人と比較して不安になることではなく、脳の80%が出来上がる3歳までに子どもにとって良い環境を整え見守り、ときには適度なお手伝いをすることです。
- 家で赤ちゃんと二人きりで何をしたらいいのかわからない
- SNSに振り回されずに子育ての軸を持ちたい
- 賢い子になって欲しい
という方はぜひすくべびのメールマガジンを登録してみてください。