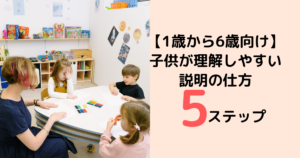子どもの才能を引き出すには、親は何をしてあげられるのでしょうか。
結論から伝えると、瞑想は子どもの才能を最大限に引き出すおすすめの方法です。
近年アップルウォッチやスマートフォンのアプリでも瞑想のアプリを勧めたり、ヨガが浸透してきたため、瞑想やマインドフルネスと言った言葉が少しずつ浸透してきました。
そんな瞑想は大人だけではなく、子どもにもとても効果的です。
事実、私たちが運営する子ども向けのスクールでも、1980年代から瞑想に取り組んできましたが、子どもやその保護者から、瞑想に取り組むことで「物覚えがよくなった」「子どもが落ち着いた」とこのように、さまざまなメリットを感じているという声をたくさんいただきます。
ここでは、子どもの才能を最大限に引き出す瞑想のメリットや取り組み方について3つお伝えします。
①なぜ瞑想は子どもの才能を引き出すのか
②何歳から瞑想ができるのか
③効果的な瞑想の取り組み方
1つずつ説明しますね。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①なぜ瞑想は子どもの才能を引き出すのか
なぜ瞑想をすることで、子どもの才能を引き出すのでしょうか。
それは、深呼吸をすることで脳からセロトニンとオキシトシンというホルモンが分泌され、体がリラックスします。
また、脳波がアルファ波になり、集中力と記憶力の向上につながります。
そのため、勉強やスポーツ、もしくはテストのときなど自分で簡単な瞑想をすることで、いつもより深く集中し、より良い結果を出すことができるのです。
また子どもたちは年齢を重ねながら、自身で上手に自分の感情をコントロールする必要があります。
- テスト前で緊張している
- 友達とケンカしてイライラしている
これ以外にも普段の生活の中で、自分の感情が高まることがありますが、この様なときに自身で自分の感情をコントロールする必要があります。
感情をコントロールするには、人に話を聞いてもらうなどさまざまな方法がありますが、その中でも瞑想は自分一人で、どこでも気軽にできるおすすめの方法です。
②何歳から瞑想ができるのか
瞑想は2歳から3歳の子どもでも取り組むことができます。
瞑想というと、ものすごく奥が深く鍛錬が必要に感じ、子どもにできるのだろうかと不安になる方も多いのですが、難しく考える必要はありません。
親子で一緒に深呼吸をするだけで瞑想につながるのです。
ただし、小さい子ども達には言葉で言っても伝わらないので、親子で一緒に取り組むことが必要です。
例えば、親子で一緒に「お母さんと一緒にやろうね。大きく息を口から吐いて。ふー。鼻から吸って。はー」と親がわかりやすく深呼吸を促すだけで、子どもは真似をします。
深呼吸をするだけですが、それも立派な子ども向けの瞑想になります。
ときには目を閉じたり、両手で隠しながら取り組んでも良いでしょう。
目を閉じながら深呼吸をすることで、目からの情報が遮断され、より深く集中できます。
普段から元気で飛び跳ねている子どもたちは、日々の生活の中で立ち止まり、深く呼吸することはありません。
また数多く習い事などをして、休む暇がない子どもも増えています。
そのため、意識的に深呼吸をすることで、リラックスし、気持ちを落ち着けたり、集中力を引き出すことができます。
③効果的な瞑想の取り組み方
子ども向けにアレンジした簡単にできる瞑想の取り組みかたは次の通りです。
- クラシックなど心の落ち着く音楽があれば流す
- 椅子に座る(大人の場合は浅く腰掛けて座る)
- 軽く目を閉じ深呼吸をする
- 心が落ち着いてきたら流れている音楽や生活音に耳を傾ける
1つずつ説明をしますね。
①クラシックなど心の落ち着く音楽があれば流す
もしご家庭に、クラシックのCDがあれば流しましょう。
モーツアルトがおすすめです。
心が落ち着く穏やかな曲調であれば、あなたの気に入っている音楽で大丈夫です。
音楽がなくても大丈夫です。
気軽に続け習慣化することが大事です。
②椅子に座る(大人の場合は浅く腰掛けて座る)
ご家庭にある椅子に座りましょう。
ご家庭に子ども用の椅子があれば、子どもは深く腰掛けます。
そして背筋を伸ばします。
あぐらを組みながら子どもと一緒に床で取り組んでも良いでしょう。
③軽く目を閉じ深呼吸をする
深呼吸をするときは4つのポイントがあります。
深呼吸をするときは、目を閉じた後、
- 口から息を吐く
- 鼻から息を吸う
- 可能であれば数秒息を止める(無理な場合はしなくていい)
- 口から息を吐く
これを一つの流れとして、上記を3回繰り返しましょう。
ポイントはゆっくり呼吸をすることです。
ただし子どもはゆっくりと息をすることができないので、すぐに息を吸ってしまいますが、繰り返し練習することでできる様になります。
人によっては手の平や、お腹、足の裏が暖かく感じる人もいますが、それは上手に瞑想ができている証拠です。
④心が落ち着いてきたら流れている音楽や生活音に耳を傾ける
子どもの様子をみて、「少し落ち着いたかな」と感じたら、次の3つに取り組んでみましょう。
- そのまま無の時間を過ごす
- 子どもに今日1日どんなことがあったのか会話をする
- 目を閉じた状態で当てっこゲームをする
1つずつ説明しますね。
①そのまま無の時間を過ごす
子どもなので落ち着かないことも多くありますが、繰り返すうちに数秒、数十秒と落ち着いてきます。
そのまま「無の時間」を一緒に過ごしてみましょう。
親子で一体になる感覚を楽しみましょう。
就寝前の瞑想は、脳波がアルファ波からシーター波に切り替わり、ときには眠くなりますが、それは睡眠の質を向上させます。
寝る前に瞑想に取り組み、そのまま寝てしまっても大丈夫です。
②子どもに今日1日どんなことがあったのか会話をする
その日どんなことがあったのか1日を振り返る方法も良い方法です。
目を開けていても閉じていてもどちらでも大丈夫です。
一つだけ注意点は主役は子どもなので、子どもの話したいという気持ちを引き出しましょう。
「今日は園でどんなことがあったの? そうなのね」と全てを受け止め、子どもの話を聞いてあげましょう。
瞑想というと何も考えない時間を過ごすイメージをお持ちの方が多いのですが、子どもに今日1日の出来事を話してもらいアウトプットすることで、頭の中が整理されます。
③目を閉じた状態で当てっこゲームをする
心が落ち着いたら、目を閉じて五感を使った遊びをしましょう。
例えば子どもが目を閉じた状態で、
- 果物の匂いを当ててみる
- タオルなどを触らせて、どんな感触が言ってもらう
- 積み木を渡して、どんな形かを言ってもらう
目を閉じた状態で集中し五感を使うことで、日常では味わえない刺激を受けることができます。
またこの方法は右脳を刺激し、子どもの想像力を高めます。
この方法は日中がおすすめです。


まとめ
瞑想というと少し難しく感じる方も多いのですが、手軽に取り組みましょう。
朝起きてから取り組んでもいいですし、眠くなる方は寝る前に取り組んでも良いでしょう。
また子どもが園で何か嫌なことがあって落ち込んでいるときや、気分が不安定な日などは、その日の夜取り組むことで、頭の中のモヤモヤがリセットされます。
毎日やろうと思うと継続することが大変なので、できるときに短時間繰り返すことが習慣化のコツです。
参考資料:https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/5/52175/20220407103331880217/HPR_21_71.pdf