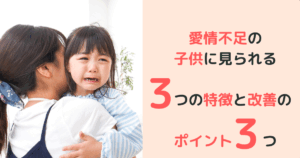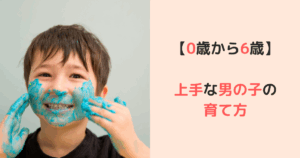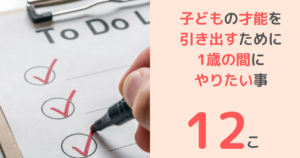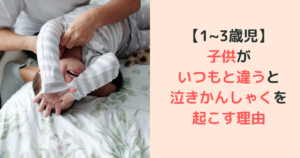毎日の生活の中で家事に洗濯と、親はやることがたくさんあります。
日常生活の中で、『少しの間だけでも子どもが一人で集中して遊んでくれたら、夕ご飯の支度がはかどるのに』と思ったことはありませんか?
しかし忙しいときに限って子どもが「ママ! 見てみて!」と声をかけてきたり、「ママじゃなきゃいや」といわれあやしていると毎日の雑務がなかなか終わりません。
こんなとき、子どもが一人で遊べるようになるにはどうすればいいのでしょうか?
実は子どもが一人で遊べない理由は性格ではなく、親の接し方に原因があることをご存じですか?
子どもが一人で遊べなくなる誤った親の接し方は次の7つです。
- 子どもと一緒に遊ぶ
- 親がすぐに子どもの機嫌をとる
- 子どもとの約束を忘れる
- 子どものそばに親が常に近くにいる
- 子どもへの過保護・過干渉
- 親が選ぶ
- 手先を使った遊びが少ない
これらの7つを見直すことで子どもたちは一人で遊べるようになり、結果親も毎日の生活がスムーズになります。
1つずつ説明しますね。
忙しい方、または音声で聞きたい方は以下の動画を参照してください。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録をよろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①子どもと一緒に遊ぶ
「え? 子どもと一緒に遊んじゃいけないの?」
と驚く方も多いのですが安心してください。
もちろん子どもと一緒に遊んでも問題ありません。
しかし、子どもたちは生まれてきた環境に適応するために毎日全身を使って遊びながら実験をしています。
子どもが一人で遊び始めたら、その時間を尊重しましょう。
これにより、子どもは自ら集中力や観察力を育み、次第に一人で遊べるようになります。
例えば、赤ちゃんがボール遊びをしているとき、ボールを触って『ツルツル』『ザラザラ』など感覚を確認したり、ボールに触れて転がる様子を観察することで、さまざまな発見をしています。
そのとき子どもたちはものすごく集中をしていますが、親が話しかけることで集中力が途切れます。
親が無意識のうちに続けることで子どもは遊ぶことに対して集中しづらくなります。
また一度集中力がなくなると再度集中するまでに時間がかかります。
想像してみてください。
せっかく映画館で迫力を楽しもうと思ったのに、隣の人が上映中に明るいスマートフォンをいじっていたら気になりますよね。
子どもたちも同じです。
集中しているときに声をかけられると親に注意が行ってしまい集中力が途切れます。
そのため子どもが遊び始めたら話しかけず静かに見守りましょう。
他にもよくある例として、子どもが集中してお絵かきをしているとき
「何かいているの?」
「すごいね」
と、このように子どもたちに声をかけていませんか?
それも集中力が途切れてしまいます。
子どもが集中している姿を見ると親はついいろいろと気になり話しかけたくなりますがそこは少し我慢しましょう。
子どもが自ら話しかけてきたり反応があるまで待つことで、子どもの集中力は育まれ子どもが一人で遊べるようになります。
ちなみに子どもたちは大体4か月ごろから一人遊びができるといわれています。
そのような姿が見られたら何も言わずに優しく見守りましょう。


②親がすぐに子どもの機嫌をとる
生後間もない赤ちゃんにとって一番のおもちゃはなんなのかご存じですか?
それはガラガラでもボールでもなく、子どもが泣いたり笑ったりしたらすぐに駆けつけてくれる親です。
子どもは大好きな親が自分が反応するたびにすぐに駆けつけてくれると赤ちゃんは嬉しくなりさらに泣いたりして親を求めるようになります。
ちょっと想像してみてください。
おなかがすいたらすぐにご飯を用意してくれ機嫌が悪ければあやしてくれる。
それが当たり前になると子どもたちは親に依存を始めます。
親に依存し始めると、子どもはすぐに泣いて合図を出すようになります。
例えば子どもが
「あのおもちゃが欲しいな。届かない」と
泣くとすぐに親が駆け付け
「これが欲しいの? あれが欲しいの?」と
対応してくれたら
「私が泣いたら親がいつでも代わりにやってくれる」
と勘違いしてしまいます。
そして子どもはそれが親とのかかわり方の正解だと学習してしまいます。
もちろん子どもに対して働きかけは必要な活動ですが、なんでも子どものペースで泣かれたら
私たち親もつらくなります。
そうならないためにも赤ちゃんのころから親子で適度な距離で過ごす必要があります。
たとえ話すことができない赤ちゃんでも実は目で訴えたり指差しをして合図を出しています。
子どもの全ての合図を汲みとる必要はありませんが気が付いたらその時は対応してあげましょう。
そうすることで子どもは「泣く」という合図ではなく目線で合図を出したり指さして教えてくれるようになります。
子どもが泣いたらすぐに反応せず危険がないのであれば少しの間見守ることで、子どもは親以外に興味関心を寄せ一人であそべるようになります。

③子どもとの約束を忘れる
みなさんはお子さんとの小さい約束を守れていますか?
子どもたちはパパ・ママが大好きです。
子どもたちにとって親は世界の中心であるといっても過言ではありません。
しかし大好きな親が約束を守らないと、子どもたちは大きな不安を感じ始めます。
子どもは不安を感じると親から離れることがストレスになり、一人で遊べなくなることにつながります。
例えばスーパーに行って子どもが
「お菓子が欲しい」
と言ってきたら
「また今度ね」
とつい気軽に子どもと約束していませんか?
親は忙しいので子どもとの小さい約束を忘れがちですが子どもはずっと覚えています。
そして
「いつ買ってもらえるんだろう」
とドキドキ・ワクワクしているのに親が忘れてしまったら子どもはがっかりします。
そしてそれが何度も繰り返されることで、子どもは不安を感じ一人で時間を過ごすことができなくなります。
子どもに不安を感じさせないためには、ダメなときに軽々しく約束せず、『ごめんね、今日はお菓子を買わないよ』ときちんと断りましょう。
他にも、
「すぐに戻ってくるからまっててね」
と言ったのについ忙しくて全然親が戻ってこないこんなことをしていませんか?
このようなことが続けば子どもは不安を感じて一人で集中して遊ぶことができなくなります。
もし今子どもとの約束を守れないのであれば、
「無理なときは無理」
と断り目を見て理由を伝えましょう。
子どもは小さくてもきちんと理由を伝えれば必ず理解してくれます。
出来ない約束はせず出来る約束だけをしましょう。
そして、子どもと約束をしたら必ず守ることで、子どもが安心を感じものごとに集中できるようになります。
④子どものそばに親が常に近くにいる
子どもが一人で遊べるようになるには信頼を築きながら距離を取る必要があります。
そうはいっても親が横にいないと子どもが一人で遊べないときもあります。
そのようなときはしばらく付き添いましょう。
そして、子どもが声をかけてきたらすぐに反応してあげます。
例えば子どもが積み木で遊んでいるときに
「ママ! ブロックが高いよ!」
と親に声をかけてきたら、
即座に
「ブロック高いね」
と子どもが言った言葉をそのまま繰り返します。
これはオウム返しと言われています。
みなさんはオウム返しという言葉を聞いたことありますか?
オウム返しとは相手の言った言葉をそのまま返すという会話のテクニックです。
例えば
「ママ、お腹すいた」
と子どもが言って来たら
「そう、お腹すいたのね」
このような感じで対応します。
小さい子どもはまだ語彙力もないため大人が言う言葉や難しい言葉を使って返事をしてしまうと理解ができなくなります。
しかし、子どもは自分が言った言葉はもうすでに意味が分かって使っているのでオウム返しで返答することで親がしっかり自分の話を聞いてくれていると感じ安心します。
そして子どもは安心することで親と多少離れても一人であそべるようになります。
⑤子どもへの過保護・過干渉
毎日の生活の中で、つい子どもにたいして過保護や過干渉になっていないでしょうか。
子どもたちは毎日試行錯誤しながら様々なことに挑戦します。
その中で子どもが失敗しないように指示をだしたり、ときには間違った選択をすることもあるので、親は無意識のうちに命令をだすこともあります。
しかし、子どもたちが失敗しないようにと親が過剰に指示を出し続けたり、子どもが失敗しないようにお膳立てしたりすることで乳幼児期に大切な失敗するという経験を奪ってしまいます。
子ども時代の失敗は、大きな問題になることはほとんどありません。
多くの場合はすぐに取り戻すことができる失敗です。
しかし、その失敗する機会を親が過保護だったり過干渉をし奪うことで子どもに次の3つの悪影響があります。
- 子どもが自分に自信を持てなくなる
- 子どもの無気力につながる
- 子どもが罪悪感を感じやすくなる
一つずつ説明しますね。
①子どもが自分に自信を持てなくなる
親の過干渉・過保護が及ぼす子どもへの影響1つ目は「自分に自信が持てなくなる」です。
親が子どもに対して過干渉・過保護になるとどうしても親が先回りしてしまい子どもを失敗させないようにします。
すると子どもは失敗したときにどのように対応すればいいのか学ぶ機会がなく、その結果自分に自信が持てなくなってしまいます。
失敗したときに自分でどうすればいいのか考え修正を試みるということは子どもにとって成長のチャンスです。
例え失敗しても成功してもどちらに転んでもそれは人生の経験として積みあがっていきます。
「今回は失敗したけれど、次はこうやってみようかな」
と、このように考え実行することで子どもの自己肯定感が高まります。
②子どもの無気力につながる
親の過干渉・過保護が及ぼす子どもへの影響2つ目は
「無気力になる」
です。
小学生高学年や中学生のお子さんを子育て中の親から寄せられる一番多い悩みの相談はなんだと思いますか?
それは
「子どもがやる気がないのですがどうしたらいいのかわからない」
です。
小さいころからいつも親から指示ばかりされると積極性が失われてしまい自ら行動しようという気が起きなくなってしまいます。
それに加えて自分が
「やってみたい!」
と思ったことを
「それまだ早いわよね」
と否定されたりするとやる気がなくなってしまいます。
あなたも
「さあ、夕ご飯の支度をしよう!」
と決意したのにそのあと直ぐ家族から
「ごはんまだなの?」
と言われたらやる気がなくなりませんか?
子どももまったく同じです。
子どもが大きくなってから意欲を引き出すのは本当に大変です。
子どもは小さいころは意欲の塊でできています。
その意欲が無くならないよう気を付けましょう。
③子どもが罪悪感を感じやすくなる
親の過干渉・過保護が及ぼす子どもへの影響3つ目は
「罪悪感を覚えやすくなる」
です。
子どもに対して過干渉や過保護をすると、どうしても無意識のうちに子どもを支配してしまいます。
そして子どもが親の意に沿わないと
「どうしていうこと聞いてくれないの?」
と子どもに訴えてしまいます。
親が無意識のうちに繰り返すと子どもは
「自分はなんか悪いことしているのではないだろうか」
と罪悪感に苦しむことにつながります。
子どもが失敗する姿をみてつい手をさし伸べたりドキドキ・ハラハラしてしまうこともありますが、
そんなときは
「子どもにとって良い成長の機会だ」
とドンと構えましょう。
親の過干渉・過保護は子どもにとってあまりいいことではありません。
今一度自分が子どもに対して過干渉・過保護になっていないか見直してみましょう。
⑥親が選ぶ
子どもが親に依存し、一人で遊べなくなる親のNGな関わり方の一つとして親の都合で物事を選ぶことが挙げられます。
みなさんもつい
「このおもちゃ面白そうだよね」
「こっちの服の方が可愛いよ」
など子どものためを思って一方的に選んでいませんか?
または急いでいるなどの理由で親の都合を子どもに押し付けていませんか?
子ども達は意欲のかたまりです。
生まれたときはなんでも触れてみたい、知ってみたいなどあらゆるものに興味関心を持っていますが
年齢を重ねていくと意欲的な子と意欲的でない子どもに分かれていきます。
なぜでしょうか?
その原因の一つとして親が何でも選んでしまうからです。
子どもはいつごろから自分で物事を選べるようになるかご存じですか?
実は生後半年もすると自分で選べる力を持っていると言われています。
ただ生まれたばかりの赤ちゃんは体や言葉を使って表現できないだけです。
そんな小さいころから物事を選べるのに子どもの意思を無視してなんでも親が選ぶことで自己選択ができない子どもになってしまいます。
自分で選ぶという経験が少ないと親に何でも選んでもらう指示待ち症候群になります。
一人で遊ぶことが上手な子は自己選択力が高いです。
「私はこれで遊びたい」
「このように工夫して遊んだら面白いかな?」
と自己選択力は意欲だけでなく考える力や物事を試行錯誤する力を育みます。
しかし毎日の生活のなかでなんでも子どもに選ばせていたらいくら時間があっても足りません。
子どもの性格にもよりますが、すぐに物事を決められる子どももいれば、決められない子どももいます。
子どもが選択するのに時間がかかる場合はあらかじめ親が二択で選んでおいてその二つの中から子どもに選ばせましょう。
「今日のデザートはりんごとみかんどっちがいいですか?」
「この服とこの服、今日はどっちを着ますか?」
このようにあらかじめ大人が選んでおくことで、子どももスムーズに選択することができます。
子どもは生まれたあと園や小学校と生活環境が変わっていきますが、お家という環境で一人で遊ぶメリットの一つに自分の好きな物で好きなだけ遊べることが挙げられます。
自分で選んだことを最後までやりきる、遊びきるという経験は園やお習い事では中々できない体験です。
親が選んだものではなく自分で選んだ好きな物を時間制限なく遊べるという経験は集中力を引き出し
一人で遊べる基礎につながります。
ぜひ乳幼児期から子どもに選ばせる経験をさせてあげましょう。
環境を整え子どもが自分で選択できるように大人がアシストしてあげましょう。

⑦手先を使った遊びが少ない
「手は第二の脳」
と言われていることをご存じですか?
手には脳につながっている神経がたくさんあり、手全体や指先を使うことで脳が活性化されます。
脳が活性化されると集中力も育まれ一人で没頭して遊べるようになります。
おうちのおもちゃのなかに子どもが指先をたくさん使うおもちゃはありますか?
手先を使うおもちゃというと
- 積み木
- レゴ
- ねんど遊び
- はさみのトレーニング
- お絵かき
などがあります。
どれも子どもが好きな遊びです。
これらは1歳半以降の子どもに向いていますが赤ちゃんの時期であればうつ伏せ遊びやハイハイなども手先を鍛える遊びとなります。
ハイハイは体幹を鍛える動きなのですが実はここに手先が器用になるヒントがあります。
子どもが器用に手の平や指先を使えるようになるには3つの発達段階があります。
- 一つ目は体幹を鍛えること
- 二つ目は肩回りや腕を鍛えること
- 三つめは指先を鍛えること
子ども達の体はこの順番で発達していきます
指先を器用に使えるようになるには最初に体幹、そして肩・腕回りを鍛えることで指先が器用になります。
よく
「うちの子不器用なのよね・・・」
と相談される方がいますが、そのように感じる場合は逆に手先の鍛えるおもちゃや遊びではなく
全身運動が不足している可能性があるのでまずは全身を動かす遊びをたくさんしましょう。
普段から外遊びや園で全身運動ができる環境が整っているお子さんには、体幹や肩周りが鍛えられているため、手や指を使うおもちゃを用意しましょう。
体幹、肩・腕周り、指先は全てつながっているのでどこが今の子どもに足りないのかを分析をして
不足している遊びを用意してあげましょう。
そうすることで子どもが思った通りに自分の体を動かせ一人で遊べるようになります。
一人で遊ぶには自分で思った通りに体をコントロールできる必要があります。
人は自分の思った通りに体を動かせると喜びを感じます。
- 積み木を積みたいのにうまく積めない
- 絵を描きたいのに思った通りに線がかけない
頭ではわかっているのに上手くできなかったら嫌になります。
これらは子どものやる気につながるので発達を促すよう是非身の回りの環境を整えてあげてください。
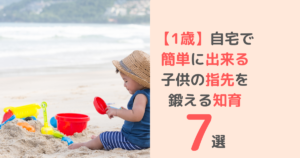


まとめ
親は毎日の生活の中で特に子どもが小さいうちは目が離せず、家事や洗濯がはかどらずストレスを感じることもあります。
子どもが一人で遊んでくれると楽だなと思うことは多いですが、それには子どもの性格だけでなく、小さいころからの親の接し方が関係しています。
親の接し方を見直すことで、子どもは一人で自立して遊べるようになります。