私たちが運営するスクールで子どもたちと関わると、「これYouTubeでみたことある」と言われることが多くなりました。
「それではこの実験やったことありますか」と質問をすると、多くの場合「やったことがない」と子どもたちは答えます。
スマートフォンや動画時代の到来で、より手軽に情報を得ることができる様になりましたが、結論から言うとできる限り本物を見せることをおすすめします。
なぜなら、
- 「知っている」と「できる」は違う
- 知っているだけのことは五感を刺激せず、記憶が定着しない
からです。
最初に1つずつ理由を説明したあと、それでは具体的にどうすればいいのかお伝えします。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①「知っている」と「できる」は違う
スマートフォンやインターネットの時代になり、大人も子どもも簡単に情報にアクセスできるようになりました。
子ども向けのコンテンツも増え、一方的に情報を受け取ることができるようになりました。
またそれに伴い子どもでも「こんなこと知っているの」と驚くことも多くなりました。
しかし、知っている二次情報だけでは再現することはできません。
我々大人は初めてのことを経験しても似た様な経験を既にたくさんしているので、過去の経験と照らし合わせて、「こんな感じかな」と想像し似た様なことを再現できます。
しかし生まれて間も無く経験も浅い子供たちは、過去に似た様な経験をまだしたことがないため「知っている」だけでは再現できません。
②知っているだけのことは五感を刺激せず、記憶が定着しない
画面越しや本での情報の知識は五感を刺激しないため、印象や記憶が脳に残りません。
実際に見て、感じて、触れて、味わうという五感を通じた刺激は、テレビなどの情報では刺激できない部分の脳を刺激します。
子どもは五感を通じた体験をして初めてそれらの情報が脳に定着していきます。
そのためできる限り質の良い本物を体験しましょう。
③具体的にどうすればいいのか
このような話をすると多くの保護者から質問をいただきます。
よくいただく質問をまとめてみました。
Q1.本物というものの、具体的に何をどうすればいいのでしょうか
A.難しく考えることはありません。お出かけをしましょう。
動物園、美術館、公園遊び、コンサート、自然体験なんでも大丈夫です。
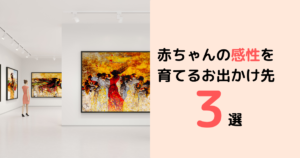
Q2.親がお仕事で忙しいため子どもに申し訳ないと罪悪感を感じます。どうすればいいでしょうか。またどれくらいの頻度ででかければいいのでしょうか
A.罪悪感を感じる必要はありません。まずはできるときに各ご家庭のペースでお出かけをしましょう。
Q3.美術館などに出かけても子どもが興味を持ってくれません
A.興味がなさそうでも実際に本物に触れてみることが大事です。
子どもが騒いでいても、大人が思っている以上に子どもは刺激を受けています。
気にせず数回挑戦してみてみましょう。
Q4.絵本やフラッシュカードなどを見せて知識を増やすことはしたほうがいいのでしょうか
A.全てを実体験で経験することは当然無理です。
そのため、絵本やフラッシュカードなどで知識や興味を増やすことは非常におすすめです。
興味は知識がないと湧きません。
また何事も知らなければ相手に対して思いやりの心も湧きません。
たくさんの絵本を読んで知識を身につけたり、フラッシュカードなどで語彙が増えたら、その後実際に本物をみて繋げることが大事です。
まとめ
知識を本や動画、フラッシュカードなどから知ることは悪いことではありません。
ただし、そのバランスがとても重要です。
知識ばかり知っていて頭でっかちでもバランスが悪いので、本物をみて五感を通じて実際に体験しましょう。
そして一番大事なことは、実際に体験してみて子どもがどう感じるかです。
一回だけではなく可能であれば、複数回体験し子どもの意見や価値観を育てていきましょう。












