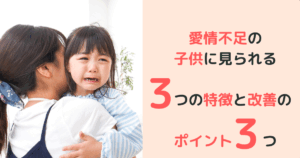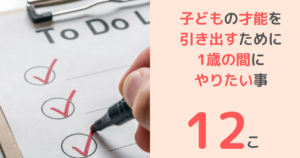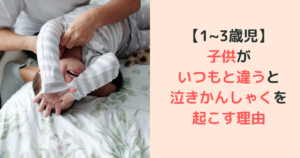「待望の男の子が生まれたけれども、どのようにそだてていいのかわからない!」
「自分の育ってきた環境に兄弟や男の子があまりいなくて、なんでこんなことするのか理解できない!」
このように感じるママは多いようです。
実は上手に男の子を育てるには、0歳から6歳の間に育んでおきたい「力」があるのです。
具体的には
- 0歳は「好奇心」
- 1歳は「やる気」
- 2歳は「集中力」
- 3歳は「自立心」
- 4歳は「我慢する力」
- 5歳は「思いやりの心」
- 6歳は「自信」
これらを0歳から6歳の間に十分に育んでおくと男の子は上手に育っていきます。
年齢順におって説明しますね。
より具体的に知りたい方は、Youtubeにて完全解説をしていますのでそちらを参考にしてください。

お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録をよろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、特典で0カ月から12カ月の赤ちゃんの発達の目安一覧表PDFデータ、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
0歳児の間に育みたい力「好奇心」
0歳の間に男の子にぜひ身につけて欲しい力は「好奇心」です。
この時期の子どもたちはまだ体を上手に動かすことはできませんが、スキンシップと言葉かけで安心感を与えて、五感をたっぷり刺激しましょう。
特に男の子はエネルギッシュな子が多いため、体を動かしたり頭を使ったりする遊びを存分に楽しむことが、心身の健全な発達に繋がります。
まだ体をしっかりと動かせないので、使うべきは音がなったりカラフルな色合いだったりするおもちゃで関わるのが良いでしょう。
また、くすぐったり、マッサージしたり、ハイハイさせたりと、スキンシップをしながら体を動かす遊びを促してあげるといいですね。

1歳児の間に育みたい力「やる気」
1歳児の男の子を育てる上で身につけたい力は自発的に挑戦する力、つまり「やる気」です。
男の子は急に手を振りほどいて走って興味の惹かれたものに向かっていくときもあります。行動範囲が広がり、集中力がついてきた成長の証でもあります。
ついつい「ダメ!危ないでしょう!」と叱ってしまいがちですが、周囲の安全確認をしっかりと行い、なるべく「ダメ!」は言わないようにしたいものです。
伸び伸びとしたいことをやってみる、やりたいものに集中することこそが「やる気」を育てることになり、これは今後の発達の土台になる大切な心持ちです。
危ない時、してはならないことをした時は、短い言葉で「座って。」「静かに。」と伝えます。また、きちんと叱れなかったときには寝る前などに振り返り、今日の行動を教え諭してあげることが効果的です。

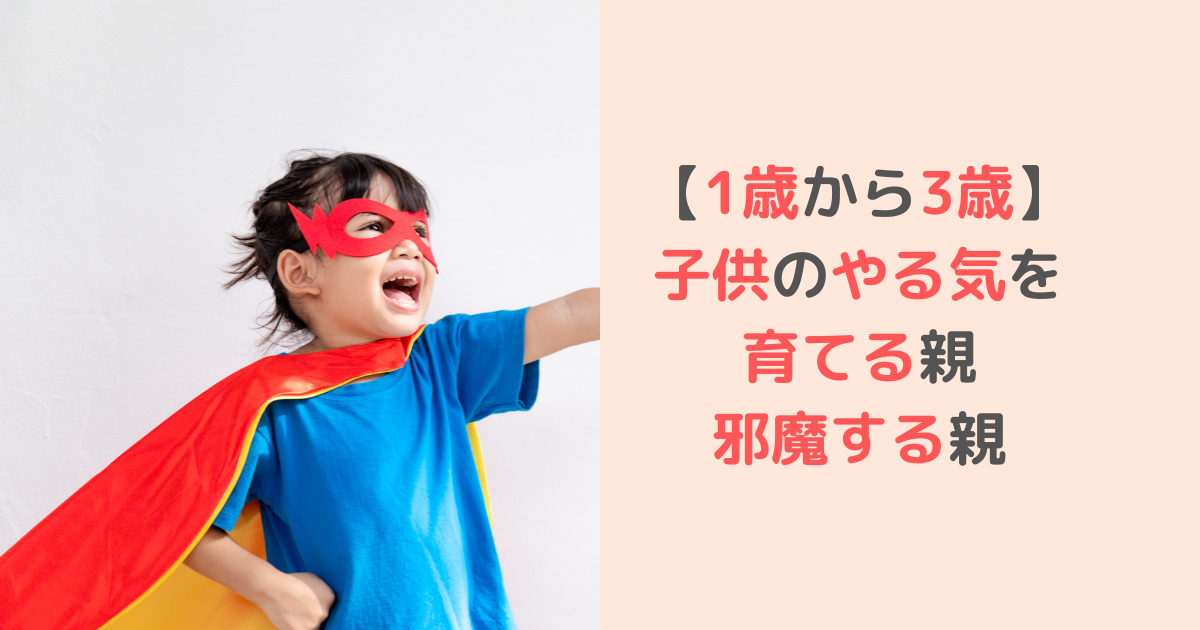
2歳児の間に育みたい力「集中力」
2歳児に大切なことは「集中力」を育てることです。集中力とは物事に没頭する力のことです。
特に男の子は電車、車、恐竜などの特定のものに強い興味を示しその世界に没頭する子どもも少なくありません。
特定のことばかりに没頭すると、ママとしてはもっと他のことにも興味をもってもらいたくなり「他にも楽しいことあるよ? これとかどう?」とつい提案してしまいますよね。
ですが、子どもが好きなことを起点として世界を広げるほうが効果的に集中力を育てることにつながります。
また、2歳児と言えばイヤイヤ期でもありますね。
ですが、イヤイヤ期は一時的な通り雨のようなもので、必ず終わりが来ます。そのことを心に据えておきましょう。
対応策としては、気持ちを言葉で表せるよう練習することです。言えないときは、保護者が代弁してあげましょう。そのようにして共感をしてあげることで子どもは落ち着きを取り戻しやすくなりますよ。
親の価値観やルールは一貫しながらも感情には寄り添うというのが効果的です。
また、保護者自身が感情のコントロールをする姿を見せることも大切です。一方でイラッとしてしまった場合は、非を見せて謝る姿も大切でしょう。
そのように関わりながら、子どもが成功したときは、「できたね。」「うれしいね。」と間違えたり遅くなっても認めてあげることが大切です。
「やり遂げたこと」に注目することがイヤイヤ期脱却への第一歩ですね。
「大好きだよ。」「〇〇くんのことがとっても大切。」などと声を掛けることも忘れずにしましょう。

3歳児の間に育みたい力「自立心」
男の子を育てる上で3歳の間に気を付けたい事、育みたい力、それは自立心です。
自立心と一言で言っても、様々な解釈があるかと思いますので、ここでの自立心とは「自分で考え行動する力」というテーマでお話をします。
3歳頃になるとイヤイヤ期の嵐も徐々に落ち着き、自己主張と協調のバランスが取れてきます。そして、少しずつ自分の体も上手に使えるようになってくるでしょう。
この時期になったら自分でできることはなるべく自分でやらせることで自立心を養うことができます。
例えば、服の着脱やおもちゃの片付けなども、失敗しながら学ぶ良い機会です。
保護者の方の中には失敗をさせたくないと思う方も多いかもしれません。ですが、新しいことにチャレンジしたから失敗をしたのです。経験を積んで、自立へと歩んでいくので、ぜひ失敗をすることも大切にしてください。
他にも親が忙しいからという理由で、親が先回りしてしまう方もいますが、それも大変もったいないなと思います。
もし忙しいのであれば「今日は時間が無いからママが代わりにやるね。今度時間のある時にやろうね」と伝えましょう。
そして時間と心の余裕があるときは親子で是非トライしてみてくださいね。
4歳児の間に育みたい力「我慢する力」
4歳頃の男の子は想像力が豊かになり、ヒーローごっこや怪獣ごっこといった遊びを通じて他の子どもと交流を深めるでしょう。
男の子のごっこ遊びというと、こういった派手な遊びを想像する方も多いのですが、おままごとでも構いません。
性別にとらわれず色々なごっこ遊びを経験させると「我慢する力」が育まれます。
4歳では友達や多くのひととかかわることで、社会性・感情のコントロール・ルールの理解・協力・リーダーシップなどが育っていきます。
ご家庭でも保護者はルールや約束をまげてまで甘やかすことなく、抱っこやしてほしいことなどについては甘やかしてあげましょう。
例えば順番は変えられないけれど、手をつないで一緒に待っていよう♩などです。
甘える気持ちは、思いっきり受け止めて、でも「ルール」は変えないようにしましょう。例え子どもが泣いても怒っても、「待つ」「守る」ことを一緒にサポートしてあげてください
大事なのは「感情はOK、でも行動のルールは一緒」というメッセージを一貫させることです。この対応をコツコツ積み重ねることで「自分で我慢する力」がちゃんと育っていきます。
5歳児の間に育みたい力「思いやりの心」
男の子を育てる上で5歳のうちに意識しておきたい事、獲得しておきたい力は「思いやりの心が持てる子」つまり他者を気遣う優しさを身に付けることです。
それではどうしたら思いやりの心が持てる子になるのでしょうか?
もし我が子に「思いやりの心が持てる子」になって欲しいのであれば、まずは家族が手本となり丁寧な言葉遣いや挨拶をする姿をたくさん見せましょう。子は親の鏡と言われるように、子どもは一番身近な存在、つまり「親」を常に観察し真似をします。
店員さんへの態度、パートナーに対する普段の言葉遣い、こういったやり取りを子どもたちはよく見ています。
友達同士のトラブルも複雑になってきますが、双方の気持ちを考えられるよう促してみましょう。子どもの気持ちをしっかりと聞いてあげることで、子どもは外へと気持ちが向いていきます。このようにして相手の気持ちを考える練習になっていくのです。

6歳児の間に育みたい力「自信」
6歳児になるとしっかりと自立し周囲が見えてくることで、不安や自信の無さも出てくるころです。6歳児の子育てのポイントは自分に自信を持てるように育てることです。
周囲と比べたり、人の目が気になって、本来できることができなくなったり、嫌がったりすることも出てきます。
小学校に上がったり、親も子どももがらりと環境が変わるでしょう。
新しい環境に飛び込むことにワクワクしている子どももいれば、不安を感じている子どももいますね。
だからこそ、大好きなパパ・ママから「大好きだよ!」「あなたなら大丈夫!」と親が子どもを信じ、愛情を伝えることで子どもはこれからの新しい世界に自信を飛び立つことができるんです。
是非たくさんの愛情を伝えてあげてください。

まとめ
「男の子だから」とか「もう3歳なんだから」と決めつけず、目の前のお子さんをよく観察して柔軟に対応していきましょう。
子どもは前に進んだり後ろに下がったりしながら成長を繰り返していきます。
保護者は、急がず、焦らず、自分のできることから始めてくださいね。
子どもの出来ないことだけに視点をむけるのではなく、成長している部分にもっともっと視点を向けて、是非今しかできない育児を楽しんでください。