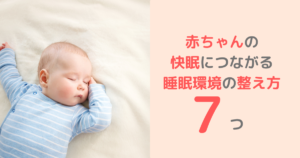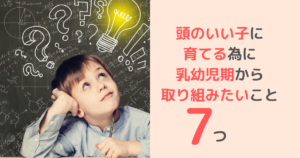子どもにはたくさんの絵を描いて、自由な発想力を養って欲しいと願う親は多いのです。
しかし、園や幼児教室でたくさんの作品を描いたり作ってくると、収納や保存先をどうすればいいのか悩むお母さんも多いです。
「子どもが心を込めて作って描いた作品をどう管理していますか」とよく質問をいただくので、保護者のみなさんがご自宅でどのように管理しているかをまとめてお伝えします。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録をよろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①絵の展示・収納方法
絵の展示・収納方法は以下の4つがおすすめの収納方法です。
①写真立てに入れる
②額縁に入れる
③ラミネート加工をする
④スケッチブックに貼る
1つずつ説明しますね。
①写真立てにいれる
小さいサイズの絵であれば写真立てに入れて飾る人も多いです。
たくさんある作品の中からこれぞと思う作品を単体で飾ると、子どもも喜びます。
賃貸で画鋲がない方におすすめです。
②額縁に入れる
少しサイズの大きいものは額縁にいれて展示しましょう。
お子さんが「ママこれ飾って!!」と、リクエストしてきたならば本人の自信作です。
お客さんが来た時にも目に付きやすく褒めてもらえるので、お子さんの自信にも繋がります。
また特別に飾ることで絵を描こうというモチベーションにもつながります。
③ラミネート加工をする
ラミネートフィルムと機械を使い、ラミネート加工もおすすめの方法です。
ラミネート加工をする機会も数千円程度で購入でき、ラミネートフィルムも小さいサイズからA3サイズまでとさまざまなものがあります。
ラミネート加工することで作品が破れたりする心配もありません。
長期間保存したい作品がある場合はおすすめの方法の一つです。
④スケッチブックに貼る
アンケートを取ると、多くのお母さんが、スケッチブックに貼ってそのまま飾っています。
表紙がしっかりした素材の物を選ぶと展示しやすいでしょう。
また、収納兼飾りにもなり、スケッチブックを閉じればそのまま本棚に収納できるので、片付けの方法としてもおすすめです。

②立体的な作品の収納方法
次によくいただく質問が、立体的な作品の収納です。
例えば粘土や工作などで作った成果物です。
特に男の子のお母さんからよくいただく相談ですが、立体的な作品については次の3つがおすすめです。
①決まった大きさの箱に入る量だけ保存する
②写真や動画などのデータ化する
③アクセサリー・クッション・マイバッグなど加工品にする
1つずつ説明しますね。
①決まった大きさの箱に入る量だけ保存する
立体的な作品は特に心がこもっており、思い出深い作品がおおいです。
そのため、決まった大きさの箱を用意し、子どもとよく相談しましょう。
そして、「この箱に入らないぐらい作品の数が増えたら、自分で優先順位をつけて捨てるんだよ」と伝えましょう。
ポイントは、子ども自身にどの作品を残し、どの作品を捨てるのか決めさせることです。
子どもの中で思い出と気持ちを整理し、優先順位をつけることで、子どもも納得します。
収納アドバイザーの近藤麻理恵さんという方をご存じですか。
今では書籍が全世界でもベストセラーになり活躍されていますが、その方がおっしゃっている「ときめくものだけを残す。ときめかないものは捨てる」という考え方があります。
作品を作ったのは子どもであり、子ども自身に何がときめくか判断させることが、子どもの想いを尊重することにつながります。
また小さいころから手先が器用な子は賢くなります。
たくさん手先を使った創作を行いましょう。


②写真や動画などのデータ化する
箱に入り切らなくなった立体的な作品については、処分する前に写真や動画を撮って保存しましょう。
ポイントは親子の共同作業で行います。
親が勝手に作品を処分する前に写真をとっても意味がありません。
子どもに撮影などもさせることで、子どもも納得します。
③アクセサリー・クッション・マイバッグなど加工品にする
中にはお子さんが作った作品をアクセサリーにしたり、マイバッグにプリントして、思い出を共有しているお母さんもいらっしゃいます。
さまざまなサービスがあるので、検索してみて自分に合うものを見つけても良いでしょう。
まとめ
絵や作品を大事に親に扱ってもらうことで、子どもの意欲が高まります。
また、意欲が高まることで次の作品を作ったり、いろいろな物をよく見て観察するようになります。
全ての作品を保存・収納することは無理ですが、上記の方法を参考にして、思い出を残してあげましょう。