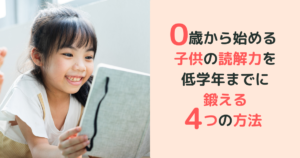子どものために、フラッシュカードをめくってみたい。
けれども、「難しそうだな」と感じたことはありませんか。
そんなお母さんでも、幼児教室のプロが教える具体的なステップで練習すれば、上手にフラッシュカードをめくることができるようになります。
ここでは私たち幼児教育のプロが画像付きで、フラッシュカードを簡単にめくることできる方法をお伝えします。
この記事を最後まで読めば、あなたも幼児教室の講師のように手際よくカードがめくれるようになります。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
カードを購入する前に、以下3つを用意する
フラッシュカードを購入する前に、必ず以下の3つを用意してください。
- フラッシュカードをまとめる輪ゴム
- 指サック
- カードをしまう箱2つ
1つずつ解説していきますね。
①フラッシュカードをまとめる輪ゴム
フラッシュカードを購入した場合、一度に大量のカードが届きます。
購入したカードは順番別には入っていますが、分類がされていません。
そのため購入後、自分でフラッシュカードを分ける必要があります。
一度にカードをめくる枚数は10枚〜15枚程度なので、輪ゴムを使いフラッシュカードをまとめ、束を作る必要があります。
②指サック
自分の指にあう、親指用の指サックを数個用意します。
親指以外の指サックは用意する必要はありません。
色々な形の指サックがありますが、フラッシュカードをめくるうちに、自分にとって使いやすい指サックが見つかります。

最初は自分の好きな色や形を選びましょう。
③カードを収納し分類する箱
フラッシュカードを市販で購入すると、一度に大量のカードが届きます。
輪ゴムで分類をしたあと箱にセットすることで、いつでも気軽にフラッシュカードをめくることができます。
プラスチック製の箱などもありますが、おすすめは紙製の組み立てる箱です。
破損して子どもが怪我をする心配や、壊れても気軽に廃棄することができます。

③カードを収納する箱2つ
フラッシュカードをめくる際、片付ける箱を2つ用意しましょう。
フラッシュカードのセット数が増えてくると、読んだカードと読んでいないカードをがまざり、仕分けるのが大変だからです。
こちらの箱はプラスチック製で自立するものがおすすめです。
以下画像のように、読む前のフラッシュカードを設定した箱を片方に起き、読み終えたら片付ける箱を反対側に設置します。
1つの束を読み終えたら、フラッシュカードに輪ゴムをして反対側の箱に片付けていきます。

箱の位置は左右関係なく、自分のやりやすい向きを見つけてください。
フラッシュカードをめくる前の心得
フラッシュカードの準備をしたら実践に移りますが、その前に以下の点を必ず確認して下さい。
- フラッシュカードのめくる時間は1日合計で3分〜5分程度
- 子どもが横を向いたりと明らかに興味を示さない場合はすぐにやめる
- 1日に数回に分けてめくる
- フラッシュカードだけでなく、外遊びやその他おもちゃなども使いバランスの良い1日を過ごす。
- 本物を見せたり、体験をさせる
- フラッシュカードのDVDやアプリだけに頼らない。
一つずつ解説していきますね。
①フラッシュカードはめくる時間は1日合計で3分〜5分程度
フラッシュカードのめくる時間は1日合計で3分~5分程度です。
ご家庭でフラッシュカードをめくる場合は、子どもの年齢や親子の慣れにもよりますが、初心者の場合、1回のフラッシュカードをめくる時間は数十秒程度でしょう。
それを1日数回、子どもの機嫌の良い時に繰り返します。
②子どもが横を向いたりと明らかに興味を示さない場合はすぐにやめる
フラッシュカードをめくっている途中で、子どもが何回も横を向き始めたり興味がない素振りをしだしたらすぐに止めましょう。
無理強いする必要は全くありません。
③1日に数回に分けてめくる
子どもが途中で興味を示さず、フラッシュカードを中断した場合は、1日に数回に分けてカードをめくります。
明らかに体調不良や、ぐずついている日は、無理にめくらず休みましょう。
④フラッシュカードだけでなく、外遊びやその他おもちゃなども使いバランスの良い1日を過ごす。
フラッシュカードは、子どもたちにとっておもちゃの1つです。
フラッシュカード以外にも、子どもの才能や語彙を伸ばす遊びは沢山あります。
親はフラッシュカードだけにこだわらず、子どもに様々な体験をさせ、バランスの良い1日を過ごしましょう。


⑤本物を見せたり、体験をさせる
フラッシュカードは絵と文字の情報しかありません。
そのため、カードで得た情報は本物を見て情報と実物を繋げる作業が必要です。
例えば、りんごというフラッシュカードを見たら、りんごを子どもに触らせ、りんごの手触り、匂い、形、繊細な色など本物にしかない情報を与えましょう。
フラッシュカードを見たあと、すぐに体験させなくて大丈夫です。
機会があったら本物に触れる経験をさせましょう。
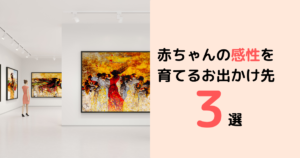
⑥フラッシュカードの動画やDVDだけに頼らない
フラッシュカードの動画、アプリ、DVDなどがあります。
お母さんが忙しい時は頼っても構いません。しかし、それだけに全てを頼ることはやめましょう。
お母さんや先生が、手動でめくることに意味があります。
手動でめくることで、親子のコミュニケーションが発生したり、先生なら子どもの顔を見て褒めたり、子どもに考えさせる間を与えることで、フラッシュカードが一方的な教材でなく、親子の触れ合いや子どもが考える時間に時間に変わります。
フラッシュカードが例えどんなに良いものでも、やり過ぎては子どもたちも嫌になってしまいます。
フラッシュカードをコミュニケーションツールとして使いましょう。
具体的なフラッシュカードのめくり方
フラッシュカードをめくるには以下の9つのポイントが必要です。
- 一度に読むフラッシュカードの枚数
- フラッシュカードをめくる注意点【0歳から3歳向け】
- フラッシュカードの持ち方
- フラッシュカードをめくる時は真上にあげるか手首のスナップを聞かせる
- カードをめくった後は手首を固定し自分も一緒に動かない
- 初心者は短い言葉や名詞からカードをめくる
- めくる言葉と文字を一致させる
- フラッシュカードを途中で落としても拾わず最後までめくる
- 主役は子どもであり、母親ではない
- 焦らず親子で楽しみながら一緒に成長する
1つずつ解説していきますね。
①一度に読むフラッシュカードの枚数
フラッシュカードは、1セット10枚〜15枚程度で、お子さんの集中力に合わせて組みます。
それらを最大20セット用意し、それを1日で全てめくります。
最初から20セット全てをめくる必要はありません。
子どもの様子を見て、機嫌が悪い時や体調不良のときは、枚数を減らしたり、めくらなくて大丈夫です。
②フラッシュカードをめくる注意点【0歳から3歳向け】
フラッシュカードは、何歳からでもめくって大丈夫ですが、ここでは0歳から3歳までの注意点をお伝えします。
0歳児の注意点
0才から6カ月までは、まだ体を動かすことができないので、集中してフラッシュカードを見てくれるお子さんが多いです。
お母さんの欲が出て、たくさんフラッシュカードをめくりたくなりますが、規定の枚数を守りましょう。
7カ月以降は、ハイハイができるようになると動き回るようになります。
その場合はカードをさっと見せて、動き回り始めたら、追加で1〜2セット見せます。
それでもフラッシュカードに興味がなく、戻って来なかったら速やかにお終いにします。
1回でフラッシュカードをめくり切れなかったら、1日数回に分けてめくりましょう。
1歳から2歳児の注意点
早いお子さんでは、イヤイヤ期に突入していたり、身体全身を動かしたい時期です。
フラッシュカードをめくり始めても、すぐに他の物に興味が移り、落ち着いて見ないでしょう。
子どもが歩き回っていても、ちらっとフラッシュカードを見たり、室内にいてフラッシュカードの言葉を聞いていたら、そのまま全てめくりましょう。
「一生懸命めくっているのに、子どもが全然見てくれない」と、イライラし相談されるお母さんも多いですが、フラッシュカードを見ていなくても、子ども達は確実に耳から情報をインプットしています。
子どもが大人しく座ってカードをみることを目標とせず、親子の時間として過ごしましょう。
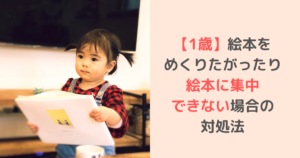
③フラッシュカードの持ち方
利き手と反対側で持ち、利き手でめくります。
フラッシュカードの裏側は、親指を立てかけると見やすい角度になります。

残りの4本の指は画像の様にし、指の上にカードを乗せます。
最初はフラッシュカードが不安定になりがちですが、慣れるとすぐに固定できるようになります。
④フラッシュカードをめくる時は真上にあげ手首を上下する
聞き手は上下に動かし、フラッシュカードを指サックにくっつける感覚でめくる。

⑤カードをめくった後は手首を固定し、自分も一緒に動かない
フラッシュカードをめくり慣れてくると、カードをめくった瞬間、自分の体が上下に動くことがあります。
フラッシュカードをめくっているお母さんの身体が上下しないよう、高さも肘を直角に締めた位置で固定します。
⑥初心者は短い言葉や名詞からカードをめくる
フラッシュカードをめくり慣れるまでは、長い単語を読みながらカードをめくる事は大変難しいです。
そのため、初心者は短い言葉や簡単な言葉からフラッシュカードを選びめくりましょう。
⑦めくる言葉と文字を一致させる
フラッシュカードがある程度早くめくれるようになると、見せる絵とお母さんの言葉がずれます。
画像のようにフラッシュカードを手に持っている段階では単語を読み上げないようにしましょう。

⑧フラッシュカードを途中で落としても、拾わず最後までめくる
フラッシュカードをめくっているとき、カードを落としたら拾わず最後まで読み切りましょう。
落としたカードは、1セット読み終えたら拾い順番を直します。
⑨主役は子どもであり、母親ではない
フラッシュカードをめくり始めると、お母さんのスキルが向上します。
慣れてくると、日に日にカードをめくるスピードが早くなり、難しくて長い単語も読めるようになり楽しくなってきます。
すると、いつの間にか目的がフラッシュカードを早くめくることになり、子どもがおざなりになることがあります。
主役は子どもであり、母親のスキル向上ではありません。注意しましょう。
⑩焦らず親子で楽しみながら一緒に成長する
0歳から3歳の間は子どもにいくら話しかけても、カードをめくっても、目に見えるアウトプット(出力)はありません。
そのため、フラッシュカードをめくりながら不安になるお母さんも多いですが、気にせず細く長くフラッシュカードをめくることを継続しましょう。
アウトプットとして覚えてきた言葉が表現できるのは3歳以降です。
実際に私たちが運営するスクールの保護者も、幼稚園や保育園に入学してから「うちの子語彙が多いな」と感じる方が多いです。
0歳から3歳の間は、インプット(入力)の時期として、焦らず長期目線で取り組みましょう。
まとめ
0歳から3歳の間に脳は80%完成されます。
そして、子ども達は身の回りの物を全てありのまま吸収していきます。
「0歳だから何もわからないでしょう」とは思わず、吸収力が良いこの時期にフラッシュカードに挑戦してみましょう。
フラッシュカードは、0歳の子どもから始める事ができる、語彙を増やす教具です。
常に子どもの目線に立ち、日常の遊びの1つとして取り組みましょう。