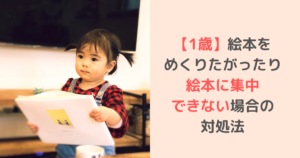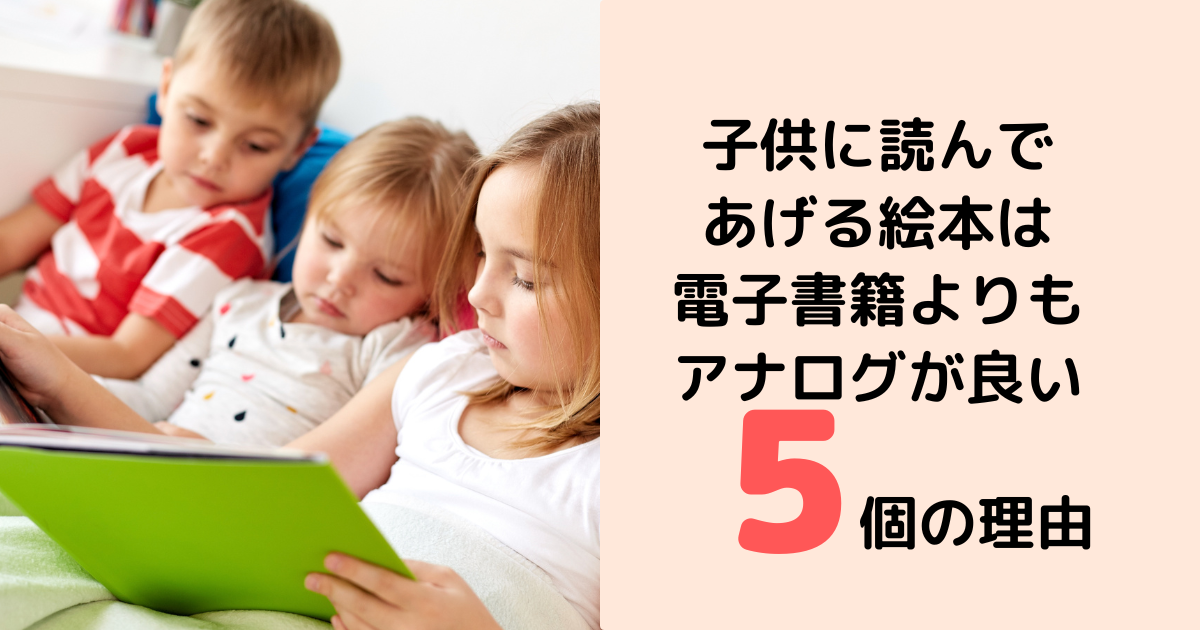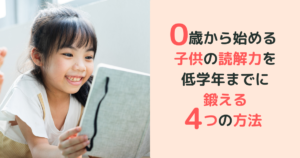子供に絵本を読んであげるとき、紙の本が良いか電子書籍が良いかについて悩んだことはありませんか?
今スマーフォトンやタブレット端末が普及してきて気軽にデジタルでも本が買えるようになりましたが、結論を言うとおすすめはアナログの絵本です。
絵本は赤ちゃんや子供たちにとって知識だけではなく、子供の精神状態を落ち着けたり、子供の好奇心を高めたり、親子の絆が深まったりする効果があります。
そんな子供たちも大好きな絵本ですが、近年スマーフォンやタブレット端末が普及してきて気軽に本が買える環境になりました。
今の時代、若いママは物心ついた時から電子機器が日常にある生活を送ってきた方もおおいでしょう。
先日あるママから「先生、子どもに読む絵本はデジタルでもいいですか? アプリや動画だと効果音が出たり、物によっては読んでくれたりするのでその方が楽なのですが・・・」と質問がありましたので取り上げてみたいと思います。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
なぜ子供にはアナログの絵本がおすすめなのか
5つの理由があります。
- 子供の様子を見ながらママが読む速度や声のトーンを変えられる
- ワーキングメモリー(短期記憶)が鍛えられる
- 絵本にさわり、絵本の重さや匂い、紙質、絵本をめくる感覚が子供にとっては大きな刺激となる
- 絵本はそれぞれ大きさが異なり、子供たちの目の能力を鍛えることができる
- 子供が少し大きくなれば自分で図書館や本屋さん赴き本と出会える
1つずつ解説していきますね。
①子供の様子を見ながらママが読む速度や声のトーンを変えられる
子どもたちは脳が未完成の状態で生まれてきます。
そのため、日々手や目などの五感を使って生まれた環境に適応していく必要があります。
ママの語りがけだけでも子供にとってはものすごく大きな刺激なのです。
書籍「0〜4歳我が子の発達に合わせた「語りかけ」育児」 サリー・ウォード著内でも実際に語りかけ育児を行い追跡調査をした結果、赤ちゃんへ語りかける効果をうたっています。
絵本は親子の共同作業です。ママが普段子供に対して語りがけをすることと異なり、一緒に物語を追っていき、子供の様子を見ながら時にはちょっと声を大きくして読んだり、抑揚をつけて絵本を読むだけでも子供たちには脳の発達を促す大きな刺激になります。

②ワーキングメモリー(短期記憶)が鍛えられる
例えば、「いないいないばあ」の遊びは乳幼児の頭を良くすると言うことをご存知ですか?
「次何がでてくるのかな?ドキドキ・ワクワク(期待)」→「ママの顔が見えた(結果)」と単純な遊びですが」、これを繰り返すことにより、短期記憶が鍛えられ物事を考えたりすることが得意になります。
絵本でも起承転結があるため、「次何がでてくるんだろう?(期待)」→「こうなった!(結果)」と同じ感覚を味わえるため、子供のワーキングメモリーの向上が見込めます。
それに加え、絵を見ながら①のようにママの読み方を変えるだけで、子どもたちはより期待をするので子供の才能スイッチを入れる相乗効果がより期待できます。

③絵本の重さや匂い、紙質、絵本をめくる感覚が子供にとって刺激となる
大人からすると本をめくるなんて大したことではないかもしれませんが、子供にとって物に触れ感覚を味わうことは成長に欠かせないプロセスです。
絵本を持ってみたり、絵本の角に触ってみたり、絵本によっては紙質も異なるので子供たちにとって大きな学びとなります。
またママと一緒に本を読むことは親子の絆を深めます。
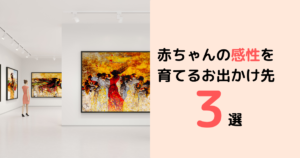
④子供たちの目の能力を鍛えることができる
私たちが運営するスクールでたくさんの子どもたちを見ていると、近年上手に目を動かせない子供が増えてきました。
幼少期から目の機能の土台が作られないまま成長してしまうと、転びやすい、疲れやすい、漢字の書き取りができないなどの問題につながることがあり、成長してから軌道修正をすることはとても大変です。
赤ちゃんにとって様々なサイズ展開がある絵本は目を鍛えるチャンスです。
子供向けの絵本は本によってサイズが異なります。
サイズが大きい絵本は子ども達の目の機能を鍛える良い教材となるでしょう。
「ここに○○があるね! あ、こっちには□□がある!」とママが絵本の絵を指を差すだけで、子どもたちはそれぞれの絵に注目し、自然と目の機能を鍛えることができます。
⑤子供が少し大きくなれば自分で図書館や本屋さんに行って本と出会えるから
電子書籍を購入する場合、検索しないとその絵本にたどり着けません。
ですが、図書館や本屋で平づみになっている本の表紙を見て気になったり、わざわざ本のある場所行って本を探す作業はデジタルでは味わえない経験ですよね。
その時にしか出会えない一冊に出会えるのはとても素敵なことだと思います。

デジタル書籍はメディアの一つとして上手に付き合う
デジタル書籍はアナログ書籍とは違い、以下に気をつけながら有効活用していきましょう。
①視聴は1日2時間程度を目安にする
文献「子どものことばの獲得過程とその問題点」によると、1日8時間以上テレビがついた状態で、かつ4時間以上テレビを視聴している子どもと、テレビの視聴時間が4時間未満の子どもでは、子供の言葉の出現の遅れに大きな差があったと指摘しています。
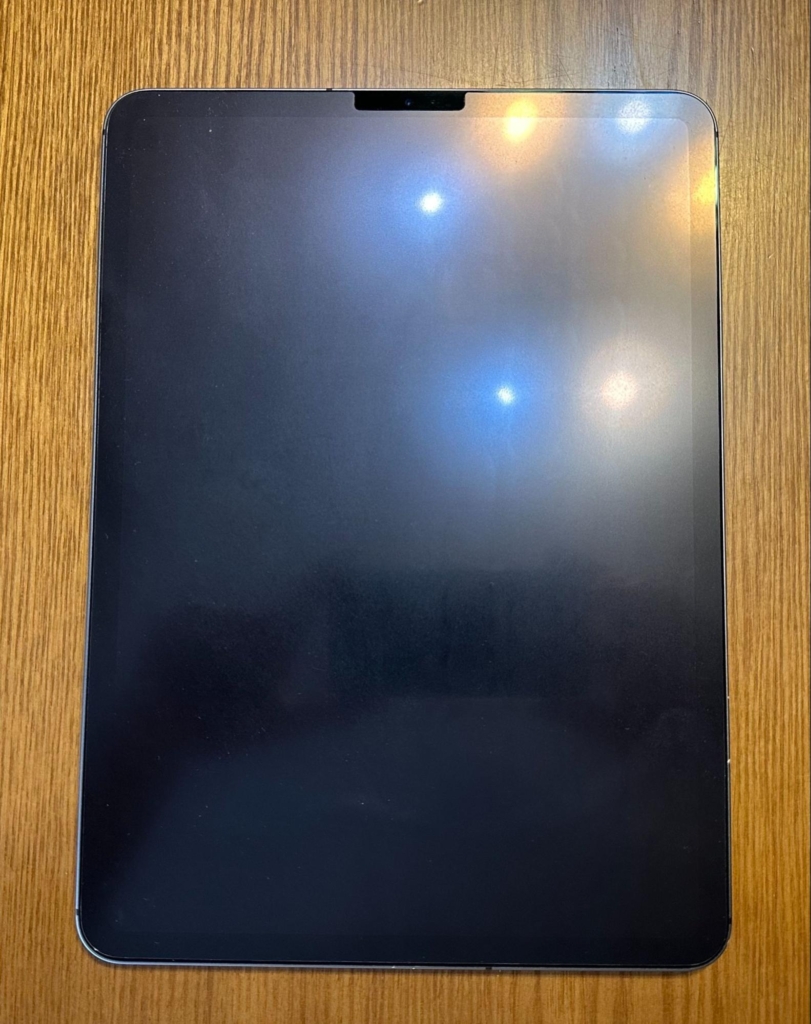
言葉の遅れという視点から考えると、テレビに限らずタブレットの利用時間、デジタル書籍などを含めて利用時間は1日2時間程度が良いです。
②1日の視聴時間が長くなった日は翌日や1週間単位で調整
デジタル書籍の利用が1日2時間となると、日によってはあっという間かもしれません。
例えば病院での待合時間で子供に静かに待ってもらいたい場合や、電車移動などがあるとスマートフォン一つで様々なことができるのでそれに頼りがちになります。
1日最大4時間程度まではデジタル書籍に触れても問題はありません。そのような場合は翌日や1週間単位でデジタル書籍の使用時間を調整しましょう。
子育てはただでさえ多忙な毎日。神経質になりすぎると継続できません。
デジタル書籍に甘える時は甘え、出来るときに調整をしていくことがポイントです。
③親子のふれあいや語り掛け、外遊びを意識する
デジタル書籍に多く触れた翌日は、親子のふれあいや語り掛けを多くしましょう。
デジタル書籍のメリットとして情報が多いことが挙げられます。
しかし、デジタル書籍は動いたり音がでるなど情報量が多い分、情報発信が一方的になり子どもたちは受け身になりがちです。
本来赤ちゃんや乳幼児はママの顔を見て表情や口の動きを見て真似をしたいという欲求を持っています。
そのためお母さんの心の余裕がある時は子供の目を見ながら語り掛けをしたり、スキンシップをしたり、お天気がよければお散歩をしたりと色々な刺激を子供たちに与えてましょう。
まとめ
お住まいの環境によっては図書館が遠く絵本を借りにいけなかったり、住まいの環境で絵本の置き場所に悩むママもいるかもしれませんが、様々な土台が作られる乳幼児期はできる限りアナログの本を与え親子の時間を楽しみましょう。