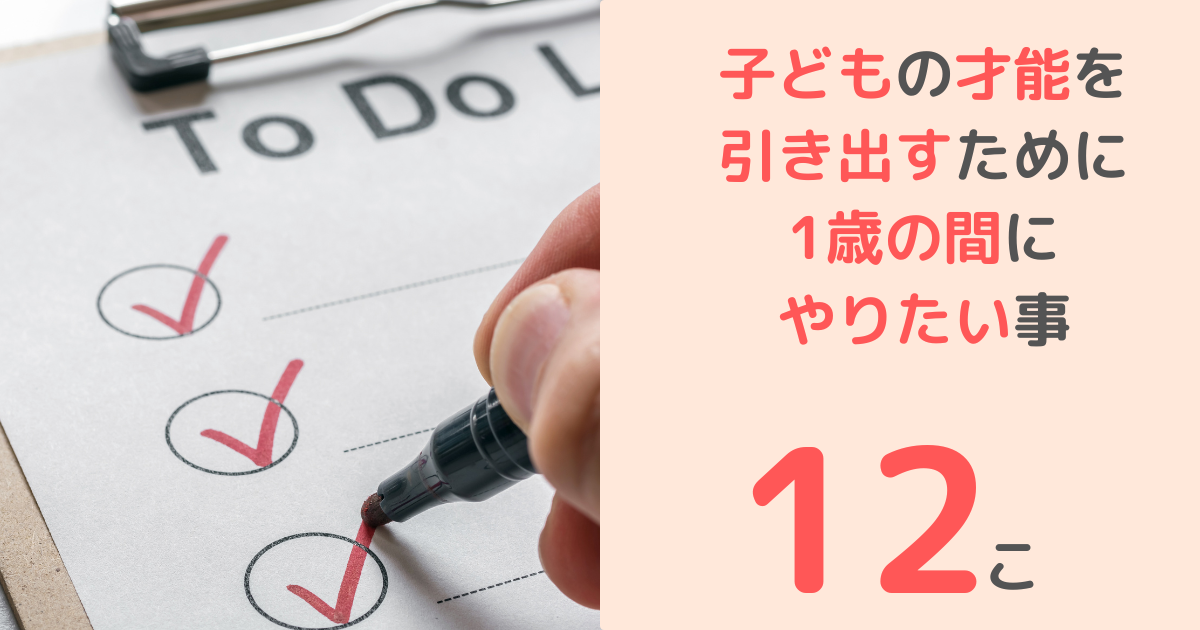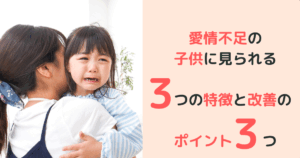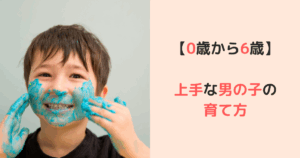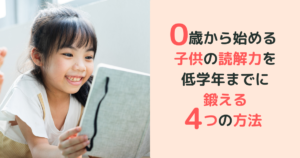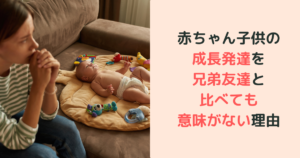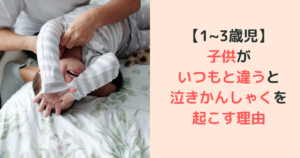多くの保護者と接する中で、乳幼児期が最も教育効果が高いとお伝えすると、『もっと早く知りたかった』という声を多くいただきます。
そして、「二人目が生まれて次男次女はできることがあればやりたいのですが、どんなことをすればいいのでしょうか」と質問も同時に頂きます。
この記事では、子どもの無限の可能性を引き出すために、1歳のうちにやっておきたい教育的アプローチを9つに絞ってお伝えします。
才能を引き出すために1歳のうちにやっておきたい教育的アプローチは次の12個です。
- 家の環境を整える
- 毎日同じルーティンにする
- 指先を使う遊びを取り入れる
- お手伝いをお願いする
- 絵本をたくさん読む
- スクリーンタイムは控えめにする
- たくさん歩き外遊びをする
- 本物を見せる
- 刺激が強いものは避ける
- 社会性を育む
- 共感と代弁をする
- 自分自身を大切にする
1つずつ説明しますね。
より詳しく知りたい方、音声で学びたい方は以下の動画を参考にしてください。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①家の環境を整える
子どもの才能を伸ばすには、子どもが伸び伸びと過ごせる環境を整えることが大切です。
特に多くの時間を過ごすご家庭での時間は子どもに大きな影響を与えるでしょう。
そのためまずは家の環境を整えます。
家の環境を整えるとお話しすると、家の広さを想像する方もいますが、ご自宅の環境は人それぞれです。
それよりも大事なことはお家の中で一か所でも一部屋でもいいので子どもが安全で、安心な時間を過ごせる空間が用意することが重要です。
個人差はありますが、大体1歳から1歳3ヵ月頃になると子どもたちは歩き出して、1歳半になるとしっかりと歩けるようになります。
ハイハイの時期は行動範囲がまだ狭かったものが、歩くようになると一気に行動範囲が広がるため、まずは家の中の安全対策を今一度確認してみましょう。
例えば
・開けて欲しくない棚にはロックをかける
・入って欲しくないエリアにはゲートを設置する
このような感じです。
そして次に安全対策を今一度チェックしたら、子どもが自立できる環境を意識します。
具体的には一人で手洗いやうがいができるように踏み台を用意してみましょう。
「まだ上手に歩けません。気が早くないですか?」という質問をよくいただきますが、子どもの成長はあっという間
先回り用意しておくことが吉です。
そして家の中の安全対策や子どもが一人で自立できる環境を用意したら、最後におもちゃや子ども用の椅子と机を用意します。
まずはおもちゃについてですが、1歳の間に揃えたいおもちゃはどんなものがあるの?と疑問に思った方もいるのではないでしょうか
そんな方はこちらの「1歳の間に絶対に揃えたい赤ちゃんの健全な発達をうながすおもちゃ 完全解説」で説明していますので、お時間のある時にご覧ください。
どれもベーシックで定番のおもちゃですが参考になります。
おもちゃを整えたら次に意識したいことは子ども用の机と椅子です。
「まだ早くないですか?小学校入学までは簡易的な物でもよくないですか?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、
・自発的な活動を促すことができる
・机に向かう習慣がつく
・体幹が鍛えられ正しい姿勢を身につけることができる
といったメリットもあるので、ぜひ1歳から用意してあげたい環境の一つです。
クレヨンを使って簡単なお絵かきなどもいずれは挑戦して欲しいので、1歳半ごろを目安に、机と椅子を用意しましょう。
家庭で意識したい3つのポイント
この時期意識したいこととして、家の中の環境は出来る限りいつもと同じを心がけるということがおすすめです。
子どもたちは生まれた環境に適応するために、毎日五感を通じてもの凄い勢いで情報を吸収していきます。
そして収集したデータをもとに毎日の時間を安心して過ごすことが出来るのですが、いつもと違うイレギュラーなことが起こると混乱し不安になってしまいます。
それでは具体的にどのような点に注意すればいいのでしょうか?
ここでは3つのポイントがあります。
1つ目、家の中の家具などのものはいつも同じ場所に置いておく
2つ目、なるべく同じ場所に座る
3つ目、毎日繰り返すことは出来る限り同じ順番にする
以上の3つです。
一つずつ説明しますね。
家の中の家具や道具はいつも同じ場所に置いておく
特に大きい家具などは子どもにとってはわかりやすい目印となり行動の指針となります。
大きな家具以外にも、おもちゃ箱はここ、机はここ、時計はここというように、家具やおもちゃなどはいたずらに模様替えせず、いつも同じ場所に置いておきましょう。
私たち大人も普段料理をしている自宅のキッチンであれば、どこに何があるのかがわかっているので安心して料理ができますが、知り合いの家のキッチンで料理をしたらどうでしょうか?
多分多くの方が「スプーンどこ? 包丁はどこ?」と戸惑いますよね。
子どもたちもまったく同じなんですね。
そのため出来る限りいつもと同じ場所にものを置いてあげましょう。
なるべく同じ場所に座る
座る場所はいつも同じにしましょう。
食卓でいつもと違う椅子にお父さんが座ったら、理由もなく子どもが癇癪を起し始めたというのはよく聞く話です。
大きな家具と同様で、認識しやすい家族は子どもたちにとっては生活をする上で大きな指針となります。
パパはいつもここに座る
ママはいつもここに座る
だから僕はここに座る
このような感じです。
そのため座る場所を固定することで、子どもが「いつもと同じ」と感じ安心します。
他にもいつもと同じという観点では、授乳する場所やおむつを交換する場所、寝る場所なども同じにすることで子どもたちが落ち着き、スムーズに環境に適応できるようになるでしょう。
毎日繰り返すことは出来る限り同じ順番にする
例えば
・服を着るときのズボンから履かせる、上着から着させるなどの順番
・靴下を履くときの右足・左足の順番
・お風呂で体を洗う順番
大体このような順番ってきまっていませんか?
これら順番も同じにすることで子どもたちもスムーズに対応することができるようになります。
出来る限りで構いませんので、同じ順番を意識してあげましょう。
他にも毎日食事で使う食器を同じにすることもおすすめです。
②毎日同じルーティンにする
大体ざっくりでいいので、毎日の生活リズムを整える、つまり毎日同じルーティンにしましょう。
毎日の生活リズムとは具体的には、朝何時に起きて、何時ごろに朝食を食べるなどの1日の流れです。
1日のリズムを整えることで、子どもたちも次に何が起こるのか、何をすべきなのかを自然と理解し子どもたちから自発的に動けるようになります。
スケジュールを決める際は、子どもの発達段階や生活リズムを尊重しつつ、親の生活リズムをベースとしたスケジュールを組むことが大切です。
大人の生活リズムを基盤にすることで、親子ともに無理のない1日を過ごせるようになるからです。
また一度スケジュールを決めると完璧にしようという方がいますが、そんなに気を張らなくて大丈夫。
1日のスケジュールを固定する目的は完璧にタスクをこなすことではなく、子どもとの楽しい時間をごすために1日の流れを考えるので、大体同じであれば問題ありません。
さまざまな都合でスケジュールが変更になる場合は朝起きる時間や寝る時間、食事のタイミングは一定に保ちながら、日中の活動内容は柔軟に調整してみてください。
肩の力を抜いて計画を立ててみましょう。
指先を使う遊びを取り入れる
手は第二の脳と言われていることをご存じですか?
手からの刺激は適度に脳を刺激してくれるといわれています。
そのため、指先を使った遊びを普段の生活に取り入れましょう。
指先を使った遊びはたくさんありますが例えば、
・シールブックなどを用意し、シール貼り遊びをする
・パズル遊び
・木琴などの打楽器を使った楽器遊び
・新聞を破ったり、丸めてボールを作ったりと新聞遊び
・つまむ動作をたくさん促すひも通し遊び
・手遊び歌
・指先に絵具をつけて遊ぶ絵具遊び
などはいかがでしょうか?
「え~、なんだか種類があって用意するのが大変!」という方はねんど遊びや砂遊びなどもおすすめです
これら遊びは手先、指先だけでなく、子どもの創造力を伸ばす良い遊びです。
他にも手にはセンサーとしての役割もあるので、器用に手先を動かす以外にも糊などを使ってベタベタする体験なんかも子どもの発達をうながす上でとても重要な遊びとなります。
どろ遊びなど服が汚れ洗濯が大変なのですが、大きくなるとなかなかできない遊びの一つなので、是非乳幼児期に経験をさせてあげてください。
以下の記事で具体的な遊びを説明しています。
参考にしてください。
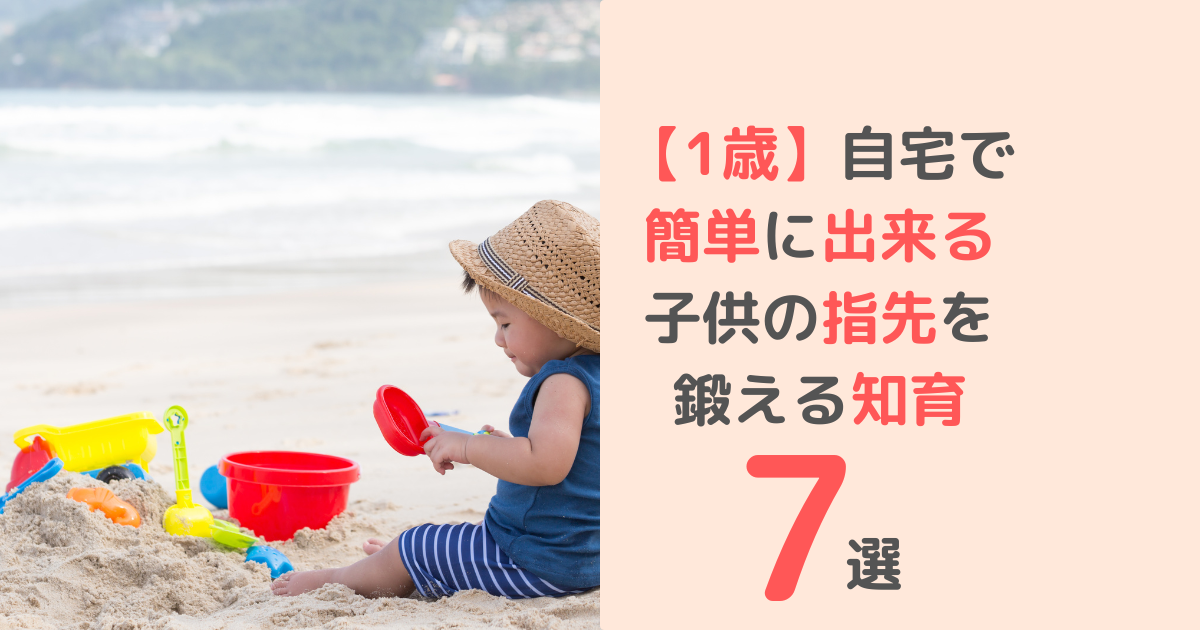
お手伝いをお願いする
1歳なると少しずつですが、親の台所のお手伝いが出来るようになります。
台所でのお手伝いを「台所育児」という言葉で例える方もいます。
台所でのお手伝いは子どもの知育にぴったりだということをご存じでしょうか?
先ほど指先を使う遊びが重要だとお伝えしましたが、台所育児には指先に加えて、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚といった五感を刺激するお手伝いにあふれています。
それでは具体的に1歳の間にできる台所育児には何があるのでしょうか?
例えば、
野菜などの食材に触れる、野菜のにおいを嗅いでみてはいかがでしょうか?
五感と脳を刺激します。
他にも野菜を洗ったり、プチトマトのヘタを取ったり、のりをちぎったりと1歳の子どもでも出来ることがたくさんあります。
実際にお手伝いをしなくても親のしている作業を見せるだけでも立派な台所育児です。
危険がないように整えて、是非親子で一緒に挑戦してみてください。
台所育児のメリットは子どもの才能を引き出すだけでなく、お子さんがいずれあなたのお手伝いを手伝ってくれる心強い味方となるでしょう。

絵本をたくさん読む
たくさん絵本を読みましょう。
子どもの才能を引き出す取り組みの一つとして絵本を読むことはよく推奨されます。
それではなぜ絵本がこんなにもおすすめされるのでしょうか?
知識や語彙を増やすためでしょうか?
そういった理由も確かにありますが、絵本読みの最大のメリットは親子の絆を深めることだと私は思います。
これから少しずつ社会性が身につき、家族以外との時間も増えてくるでしょう。
そして外の世界でさまざまなことを感じ経験してくるでしょう。
ですが、何があっても絵本を読むときだけはママやパパを独占できるといった安心感は親子の絆と愛着形成を深めます。
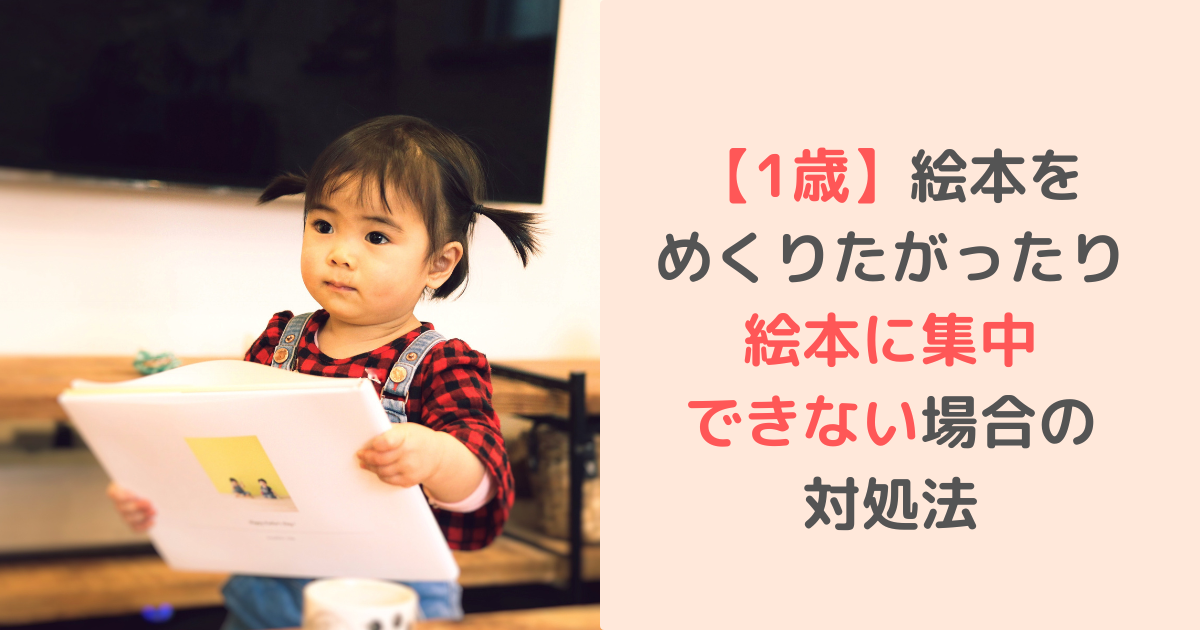
スクリーンタイムは控えめにする
スクリーンタイムとは簡単に言えば、テレビやスマートフォン、タブレット、ゲーム機などのデジタルデバイスのことを指します。
WHO世界保健機関のスクリーンタイムガイドラインでは、1歳未満ではスクリーンタイムは推奨していません。
1~4歳では、1日1時間未満のスクリーンタイムを推奨するといわれており子どもの目の健康や心身の発達に影響を及ぼす可能性があるため、保護者による指導や配慮が重要と主張しています。
つまり1歳ではスクリーンタイムは1日1時間が一つの目安となるということです。
視聴時間以外にも、画面サイズも重要です。
スマートフォンなどの小さい画面ではなく、出来る限り大きな画面で視聴し、画面から離れて視聴しましょう。

たくさん歩き、外遊びをする
ぜひたくさん歩いて、体を使った外遊びに取り組んみましょう。
たくさん歩き遊ぶことで、体の隅々に酸素がいきわたり脳の発達につながります。
このようにお伝えすると「たくさん歩くって言われてもどれぐらい歩けばいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
その答えとしては、年齢×1キロが一つの目安と言われています。
これは自宅内での移動も含まれているので、たくさんお家の中で遊んで少しお散歩すれば無理なく達成できる距離ではないでしょうか。
外にお散歩に行ったら平坦な道だけではなく、坂や草の上をたくさん歩きましょう。
そういった場所を歩くことで体の体幹やバランス感覚も鍛えられます。
本物を見せる
この時期は本物をたくさん見せてあげましょう。
本物というと、動物園や美術館などを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
もちろんそういった特別な場所も素敵なのですが、もっと手軽なのが自然に触れることです。
道端に落ちている石ころを集めてみたり、どんぐりを拾ったり、葉っぱを拾ったりと、毎日のお散歩の中で出来ることで構いません。
たくさん本物を見て、触れさせましょう。
本物を見ることで五感が刺激され、葉っぱやどんぐりをひろったりすることでしゃがんだり。目を使ったり、手先を使ったりと体全身が刺激されます。

刺激が強いものは避ける
1歳だけに限らず、3歳または4歳ぐらいまでは刺激が強いものを避けましょう。
刺激が強いものとは、五感を強く刺激するもの、印象が強く頭に残る物、他にも射幸心(しゃこうしん)煽るもの、つまりギャンブル的な要素が高いもののことを指します。
身近な物で例えると、
・砂糖などの甘いもの
・スマートフォン
・ガチャガチャ
などです。
乳幼児期の子どもたちはまだ脳が未熟なため、強い刺激を受けても自分をコントロールすることがまだ出来ません。
そのため刺激が高いものを連続して経験すると簡単に依存してしまいます。
親も「まぁ、これぐらいいいだろう」と思い与えたら、思った以上に子どもがはまってしまい、与えないと癇癪を起して大変という話もよく聞きます。
この時期の子どもたちにはまだ知らなくていいものや知らない幸せというのもあります。
そのため、刺激が強いものはできる限り避けましょう。
このような話をすると生涯禁止!という方もいますが、年齢を重ねたらどこかのタイミングで少しずつ許可をしていく方がいいでしょう。
もちろん人によりますが、ずっと禁止されるといつかその反動がきて歯止めが効かないという話もよく聞きます。
実際に私のスクールに通っている保護者の方も「小さいころから大人になって家を出るまで、家では一切お菓子や甘いものを禁止されて、大人になってからその反動でたくさん食べてしまう。一度食べるとなかなか辞めることができない」という話もよく聞きます。
そのため、年齢に応じて避ける時期、少しずつ慣らす時期、ほどほどに調整する時期などに分けるといいでしょう。

社会性を育む
1歳前後から人とのかかわりを通して徐々に自我が芽生えます。
自我の芽生えと同時に、少しずつ自己主張が強くなってくるでしょう。
さらに、1歳後半には自分のものという認識が出てきて、友達とおもちゃの取り合いになることもあります。
しかし、こういった経験も子どもの成長にとって必要ですし、子どもの世界のことは出来る限り子ども同士で解決して欲しいので、ケガの心配がないのであれば少し見守ることも必要です。
家での時間も重要ですが、少しずつ同世代のお友達と触れ合うことも意識しましょう。
また一見遊びに見えるおままごとやお店屋さんごっこも子どもたちにとっては社会性を育む良い練習です。
おままごとの付き合いはなかなか大変ですが、どうぞ一緒にたくさん遊んであげてください。
共感と代弁をする
1歳になると一語文と言って、「わんわん」や「ママ」といった幼児語を発するようになります。
そして、1歳後半から一気に言語爆発の時期が来て、たくさんの言葉を習得していくでしょう。
しかし、言葉を知ったからといってすぐに正しく使えるわけではありません。
また言いたい事と言葉が一致していないことも多々あります。
そのため、この時期の子どもたちは言葉を習得しても時には自分の言いたいことが言えず、癇癪という形で気持ちを表現することもあります。
そんなときは親が代弁したり、気持ちを共感してあげてください。
自分の口で言えなくても、親が代弁や共感をしてくれることで、子どもの気持ちも満たされていきます。
「こんな時は嬉しいっていうんだよ」
「こんな時は悲しいっていうんだよ」
このように状況に応じてこのように自分の気持ちをなんていったらいいのか子どもに教えることで、子どももどんなときにどのような言葉を使えばいいのかを学び自分の感情の表し方を学んでいきます。
子どもの脳はまだ未熟なため正しく使えるようになるには少し時間はかかりますが、焦らずゆっくりと親子で一緒に成長していきましょう。
自分自身を大切にする
子どもは親が思っている以上に、日々自立に向けて成長していきます。
そのため、子どもを信じて少し見守ってみてはいかがでしょうか?
親が子どものことを考えすぎてしまい、親・子の適切な距離が取れなくなってしまう家庭を時々見かけます。
・近すぎるからこそ、親は子どもの良いところが見えなくなる
・我が子の痛みがまるで自分の痛みのように感じる
一見共感しているように見えるかもしれませんが、親子の距離が近すぎても、子どもを俯瞰できなくなってしまいかえって悪影響になることもあります。
だからこそ、時にはパートナーに頼ったりして、少しだけでいいので自分の時間をとってリセットしましょう。
そうすることで、自分自身を俯瞰できるようになり、親子の適切な距離を取れるようになります。
まとめ
才能を引き出すために1歳のうちにやっておきたい教育的アプローチは次の12個でした。
- 家の環境を整える
- 毎日同じルーティンにする
- 指先を使う遊びを取り入れる
- お手伝いをお願いする
- 絵本をたくさん読む
- スクリーンタイムは控えめにする
- たくさん歩き外遊びをする
- 本物を見せる
- 刺激が強いものは避ける
- 社会性を育む
- 共感と代弁をする
- 自分自身を大切にする
一見たくさんやることが多く感じますが、このように体系化してみると、どれも出来ることではないでしょうか?
焦らず自分の出来ることから始めましょう。