小学校に上がったら算数が大好きな子になって欲しいと願う親も多いです。
そんなお父さん、お母さんには、子どもが小さいころから100玉そろばんを与えることをおすすめします。
具体的には1歳前後から購入して欲しい知育玩具の一つです。
ここでは、
- 100玉そろばんとは何か
- なぜ100玉そろばんがおすすめなのか
- 具体的な100玉そろばんの使い方
についてお伝えします。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
①100玉そろばんとは何か
100玉そろばんは、そろばん教室で使うそろばんとは違い、玉が10個×10行で計100個連なったそろばんです。(以下画像参照)
100玉そろばんは計算をするためにも使えますが、主な目的は子どもが遊びながら、数の量の感覚を育てることができます。

②なぜ100玉そろばんがおすすめなのか
子どもは
- 数字が書けること
- 1・2・3と数字が読めること
- 1から100まで数を唱えること
- 数の感覚を覚えること
- 計算をすること
これらをバラバラに覚えていきます。
それぞれタイミングとバランス良く触れる機会があり、習得できればいいのですが、現実にはバランス悪く習得していきます。
バランス悪く習得すると、
- 数字は書けるけれども計算はできない
- 数字は読めるけれども書けない
- 計算はできるけれども数の感覚がわからない
このようなことが起こります。
「計算できれば問題なくないですか」と多くの方から質問を頂きますが、数の感覚がわからないと、文章問題で問題を読めても問題をイメージすることができないので解くことができません。
具体的に、「アメが3個ありました。1個食べてしまいました。残りはいくつ」と聞かれても、3がいくつぐらいなのか、食べて減るとはどう言う意味なのかがわからないと想像できません。
そうならないためにも、小さいころから数の感覚を育てたり、数つかった遊びをたくさんする必要があります。
1つでその全ての条件を満たしてくれるのが100玉そろばんです。
③具体的な100玉そろばんの使い方
それでは具体的にどのように使えばいいのでしょうか。
ここでは年齢別に100玉そろばんの使い方をお伝えします。
0歳児の場合
0歳から100玉そろばんが必要なのかと驚かれる方も多いのですが、100玉そろばんは年齢にあったおもちゃのように、一時的に集中して卒業するおもちゃではありません。
小さいころから視界の中にあることで、触れて興味を持たせることが必要です。
また赤ちゃんは見たもの触れた物を全て吸収するという特性を持っています。
そのため、小さいころから数に触れておくことで、3歳以降抵抗なく計算や数遊びができるようになります。
具体的な使い方ですが、私たちが運営する教室では100玉そろばんを使い、
- 右左
- 上下
- 前後
これらを赤ちゃんと先生が向き合って、身体を傾けながら遊びます。
また、100玉そろばんを触ってもらい、左右に腕を動かし玉を移動させたり、上下に玉を動かし腕の運動やパッと離す練習も取り入れています。
ご家庭での注意点は、せっかく100玉そろばんを使ったからたくさん遊んで欲しいと思い、つい子どもに矯正してしまいますが、無理強いはやめましょう。
しかし、0歳から3歳のうちは子どもが遊び始めたら一緒に遊ぶという感覚で大丈夫です。

1歳児から3歳児の場合
1歳後半になると「これはいくつ」と質問すると、「1」「2」と今まで吸収してきたことが表現できるようになります。
3歳を迎えるころにはお話も上手になりますから、「1」は「1個」、「2」は「2個」と目で見ながら実際に100玉そろばんを動かし、言葉と数の量を一致させていきます。
そのため、以下の2つの遊びがおすすめです。
- 12345678910数を数えながら玉を移動させる
- どっちが多い遊び
1つずつ説明しますね。
①12345678910数を数えながら玉を移動させる
まずは基本の数の考え方を教えます。
お風呂に入るとき、「1から10まで数えてから出ようね」と子どもに教えている親も多いのですが、数えるようになったから数の感覚がわかっているわけではありません。
そのため、100玉そろばんを使って言葉と数の量が一致するようにします。
②どっちが多い遊び
どっちが多い遊びもおすすめです。
そろばんの玉を10個と1個見せて、どちらがおおいのかクイズを出すことも子どもが楽しめるアクティビティの一つです。
例え答えることができなくても、親が「こっちだね」と淡々と答えを教えていくことで、子どもは理解し当てられるようになります。
子どもが悩んだらすぐに答えを教えてしまいましょう。
繰り返しになりますが、0歳から3歳の間は見たもの触れた物全てをそのまま吸収するので、「子どもで理解できないから10個までにしよう」とは思わず、100までどんどん教えましょう。
3歳以降
3歳以降は以下の使い方がおすすめです。
- 逆唱
- 2とび
- 5とび
- 10とび
- 数の合成・分解・差
どれも至ってシンプルで楽しい遊びです。
1つずつ説明しますね。
①逆唱
逆唱とは大きい数から小さい数へ下がっていくことです。
具体的には10から0へ下がりながら数えることです。
100玉そろばんで数が減っていく様子を目で見ると子どもも理解しやすいです。
子どもに100玉そろばんを触らせることもいいですし、親が子どもの手を持って「10からさがっていくよ」と一緒に操作をしてもいいです。
②2とび
偶数の2・4・6・8・10の2飛びを確認する遊びです。
最初は2から10まで。
慣れたら20や30などの数にも挑戦しましょう。
③5とび
5とびは、5・10・15と増やしていく遊びです。
5から始め50を目指しましょう。
最終的には5とびで100まで言えるように目指します。
④10とび
10とびは、10・20・30と10ずつ増えていく遊びです。
最初から10から100までを目指し言えるようにします。
⑤数の合成・分解・差
数の合成、分解、差とは、簡単に言えば足し算と引き算です。
3歳以降プリント学習を始める親子も多いのですが、プリント学習のみの計算の練習になると、どうしても数字の組み合わせを覚える作業になってしまいます。
そこで100玉そろばんの登場です。
計算をプリントをするときに、同時に100玉そろばんを子どもに与え、計算をしながらそろばんを一緒に使いましょう。
そうすることで、数の感覚もわかるようになります。
またプリント以外でも、「今5個玉があります。7個にするにはあと何個必要ですか」とクイズをするように子どもと一緒に遊びます。
計算プリントばかりだとマンネリ化するので、このように100玉そろばんを活用すると子どもも楽しく数で遊べるようになります。
また「今7個玉があります。5個にするには何個取ればいいですか」と、引き算の要素をいれても良いでしょう。
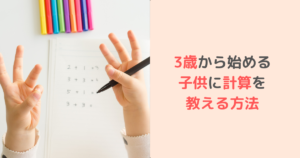
かずを自由自在に頭の中で動かせるようになることが大事
今小学校でも「さくらんぼ算」という計算に取り組んでいる学校も多いです。
さくらんぼざんとは、「10にするには、3といくつ必要ですか?7だね」というように、数を分解、合成しながら計算する方法です。
上でも述べたように、1から10まで数唱できるだけでは数が言えるだけ、計算ができるだけではその後算数でつまづく子が多くなったため、このような計算を進めている先生が増えました。
100マス計算やさくらんぼ算などさまざまな計算練習方法がありますが、どれも効果的なやり方です。
大事なことなので繰り返しますが、算数が得意になる上で大事なことは、
- 数字が書けること
- 1・2・3と数字が読めること
- 1から100まで数を唱えること
- 数の感覚を覚えること
- 計算をすること
これらのバランスです。
幼少期から100玉そろばんを使うことでこれらのスキルがバランス良く育まれます。
数を習得する上でおすすめのアイテムの一つです。
まとめ
数といっても子供にとっては、数字と量は別物です。
上の空で言えるようになるのが第1ステップ。
指を差しながら1個1個数えられるようにするのが第2ステップ。
年齢ごとに数の操作が出来るように100玉そろばんを活用してください。
目指すは、頭の中で数の操作が出来、大体このくらいかなと量の検討が付くことです。目安が分かると考え方の道筋も探しやすくなります。








