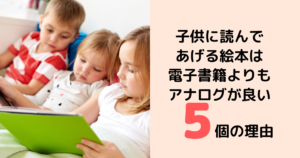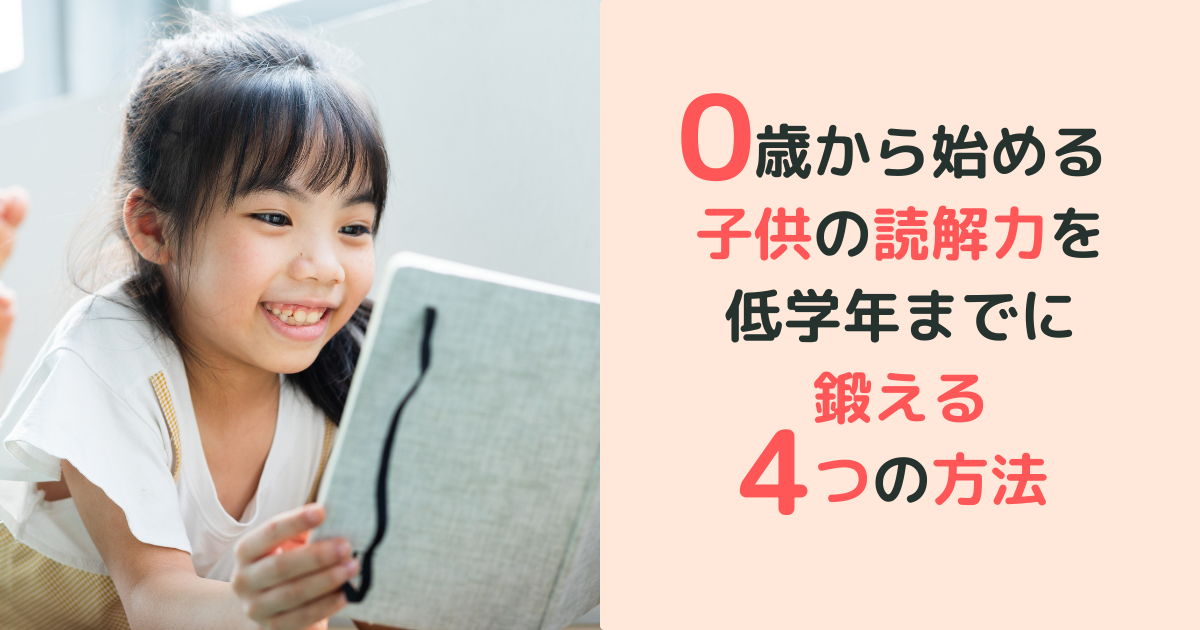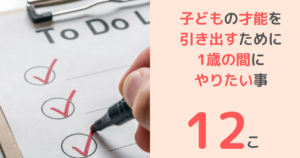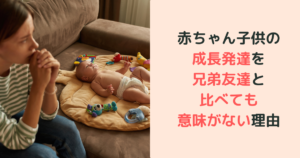将来、読解力が高い子どもになって欲しいと願う親も多いのではないでしょうか。
読解力は小学校に入学したから突然身につくものではなく、乳幼児期から適切なアプローチが必要です。
読解力を高めるには小さいころから、
- 多読(たどく)
- 精読(せいどく)
- 速読(そくどく)
- ダイアロジック・リーディング
以上の4つの読む力が土台として必要です。
どれも普段から私たち大人は無意識にしていることですが、子どもが小さい頃から意識して取り組むことで読解力が大幅に高まります。
まずは読解力を高める読み方を1つずつ説明した後、年齢別に取り組みたいことを説明します。
お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。
チャンネル登録よろしくお願いします。
お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁
本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。
気軽に登録してくださいね。
→登録はこちらから。

いくみん先生
自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。
常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。
その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。
著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。
(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)
読解力を高める本の読み方
子どもの読解力を伸ばす本の読み方は全部で四種類です。
①多読とは
多読(たどく)の基本はたくさんの本に触れることです。
読解力を伸ばすにはさまざまなおすすめの本の読み方がありますが、多読は読解力を高めるための一番の基礎です。
多読の目的は
- さまざまな本に触れること
- 文字に触れたり文書を読むことに対して抵抗感を減らすこと
- 本を読む楽しさを知ること
があります。
多読は国語の問題を解くために読んだり、書いてある内容を100%理解するために読むことではありません。
例え子どもが途中で本に飽きて続きを読まなくても、複数同時にいろいろな本を読んでも大丈夫です。
「どうして最後まで読まないの」などと指摘せず見守りましょう。
小さいころから親子で一緒に絵本をたくさん読むだけでも多読になります。
多読はさまざまな情報を楽しくインプットする良い機会です。
小さいころからたくさん絵本に触れ、本を読むことが習慣になるように目指しましょう。
②精読とは
精読(せいどく)とは、じっくり文章を読み内容をより正確に理解することを目的としています。
意識的にじっくり読むので本を読むスピードは落ちますが精読を繰り返すことで徐々に早く精読ができるようになります。
しかし、短時間で大量の本を読むことには向いていない読み方です。
小学校入学以降、教科書や文章問題読解などに必要な力となります。
③速読とは
速読(そくどく)とは本を早く読む能力のことです。
速読にはさまざまな流派がありますが、子どものうちは以下2点を目標としましょう。
- 眼球を早く動かし本を読むこと
- 目的の情報を探し出すこと
1つずつ説明しますね。
①眼球を早く動かし本を読むこと
近年便利な時代になるにつれて、眼球を上手に動かせない子どもが増えています。
眼球を上手に動かせないと
- 読み間違いをたくさんする
- 文章の1行目から2行目に変わる瞬間どこをみていいのかわからなくなり、全く違う行を読み始める
このような問題を抱えている子どもが増えています。
そのため小さいころから目を上手に動かせるようになる必要があります。
②目的の情報を探し出すこと
速読の目的の二つ目はパラパラと本をめくり自分に必要な情報を取り出すことです。
我々大人も今晩作るメニューをレシピ本から探したり、目次から目的のページを探すことをしますがそれも速読の一つです。
素早く情報を見つけ処理する方法は勉強だけでなく、将来ビジネスや日常生活においても必要な能力です。

④ダイアロジックリーディング
ダイアロジックリーディングとは、親が本を読みながら、
- 話を聞いてどう感じたのか
- 主人公の名前は
- 登場人物は何人
- 要約させる
このように質問しながら本を読むことです。
ダイアロジックリーディングをすることで、思考力や要約する力が育まれます。
②これら4つの読み方を年齢に合わせて使い分け読解力を伸ばす
少し専門用語が続いてしまいましたが難しく考える必要はありません。
子どもの様子をみて、その時々で色々な読み方に挑戦してみましょう。
①0歳からハイハイ期まで
赤ちゃんは五感を通じてさまざまな情報を吸収しています。
この時期は特に耳から入ってくる言葉にはとても敏感でスポンジで水が吸収されるように聞いた言葉はどんどん脳に吸収されていきます。
そのため生まれてハイハイをするまでは多読が向いています。
時間のあるときに絵本をたくさん読んであげましょう。
またたくさん語りかけてあげることで語彙が増えます。
0歳から3歳まではインプットの時期と言われており赤ちゃんにこのように働きかけても目に見える発語などはありません。
しかし小さい頃から働きかけてきた親からは「3歳まではよくわからなかったけれども、園に入園して他の子と接してみると、確かに我が子はおしゃべりでいろいろな言葉を知っていて説明が上手なので意思疎通ができる」という声をよくいただきます。
積極的に読み聞かせ・語りかけをしましょう。

②歩行期から3歳にかけて
1歳前後から歩き始める子どもも増えるでしょう。
そのため、絵本を読み始めても最後までお話を聞く前に歩いてどこかに行ってしまう子どもが増えますが、どこのご家庭でも相談される悩みの一つです。
親も0歳からハイハイ期までは絵本を最後まで読む習慣が身に付いているので気になる方が多いのですが、この時期は戦略を変えましょう。
歩行期から発語前までは簡易版ダイアロジックリーディングがおすすめです。
ダイアロジックリーディングとは子どもに質問をしたり要約をさせたりすることですが、この時期は発語ができないため、絵本を開きながら子どもに質問をしましょう。
例えば「りんごはどれ。クマさんはどれ」と質問をし、子どもに指差しで答えてもらいましょう。
この方法はエリアにもよりますが1歳半検診などでも子どもの語彙の確認のために使われている方法です。
0歳から語りかけたり絵本を読んでいれば子どもは頭の中に名前とものの情報をインプットし答えることができます。
絵本を最後まで読むことを目的とせず、親子のコミュニケーションの一つとして取り入れてください。
親が質問し答えることも立派なダイアロジックリーディングですし、何よりも親子で一体になって取り組むことが子どもの前向きな心を育みます。
またこの時期は「同じ絵本を何度も読まされる」と悩まれる親も多いです。
個人差はありますが2歳ごろによくみられる光景です。
そのような場合は子どもが覚えるまで何度も繰り返し同じ本を読んであげましょう。
親は同じ本を繰り返し読まされるとうんざりする方も多いですが、精読から暗唱につながるので是非根気よく読み続けてあげてください。
お気に入りの本を何度も読むことで子どもが次のページをめくらなくても内容がわかったり、フレーズを言えるようになります。
さらに繰り返していくと見ないでも言える様になります。
これは暗唱といいます。
暗唱ができるとすぐに覚えられるようになったり語彙が増えたりとメリットがたくさんあるので是非幼児期から習慣化したい取り組みの一つです。
ぜひ取り組んでみましょう。
暗唱については詳しくはこちらを参照下さい。

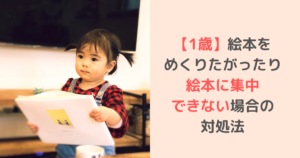

1歳から3歳の絵本のよみかたまとめ
- 子どもが落ち着いているときは絵本の多読
- 歩き回ったり落ち着かない場合は文章も読まず絵本の絵だけ見せる速読読み
- 同じ絵本を何度も読まされるのであれば精読から暗唱につなげる
- 「りんごはどれ」など質問をしながらダイアロジックリーディングをする
最後まで絵本を読むことを目的とせず、いろいろなバリエーションで絵本を読み進めましょう。
③4歳から小学校低学年にかけて
4歳以降も1歳から3歳にかけてお伝えした方法で引き続き絵本を読み進めます。
しかし大きな違いは4歳以降になると文字に興味を持つ子どもも増えてきます。
子どもの発達には個体差があるので文字に興味のない子どももいますが、ひらがななどの文字に興味を持っているようでしたら絵本を読む際に子どもが知っている文字を指さして「これはなんていうひらがなだっけ」と問いかけながら一文字ずつ文字を読ませても良いです。
子どもが知らない文字を質問したり子どもを試すようなことはやめましょう。
知らない文字が出てきたら「これは◯◯と読むんだよ」と答えをすぐに教えてあげましょう。
このように繰り返していくと小学校低学年以降に練習したい音読につながります。
子どもに文字を声にだして読みたいと思わせることが重要になります。
園児の間は子ども一人で全ての文章を読めないので、親子で順番に読み合いをすることも良いです。
音読が一人でなめらかにできるようになったら、読むスピードを早くしましょう。
早口で文章を読み、それに合わせて眼球を動かすことで速読につながります。
そして問題なく文章を順番通りに追えて、ある程度早口に文章を読めるようになったら、精読やダイアロジックリーディングを始めることでより読解力が高まります。


まとめ
子どもに読解力を高めて欲しいと願うのであれば、子どもが「本を読むことは楽しい」と思ってもらうことです。
親はつい子どもの能力を高めるために速読やダイアロジックリーディングなどを強要してしまいがちですが、子どもが楽しく感じなければどんなに素晴らしい読み方をしても読解力は高まりません。
まずは
- 本を読むことは親子の楽しい本の時間であること
- 本がある環境を親が整えること
ここから始めて楽しい親子の時間を過ごしてください。